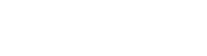
――非常に複雑だけれど、ポップなアルバムだと思いました。果たして、本作はどのようにしてつくられていったのでしょうか? 以前のインタヴューでは、ceroのアルバムと言うと構成が凝っていると捉えられがちだけれど、「最初からコンセプトを決めてそれに向かってつくっていくわけではなく、ピースができあがってくるにつれて絵が見えてくる」と語っていましたが。
髙城 それこそ、今回はモヤモヤしていた時期も長かったですからね。段々と霧が晴れるようにアルバムが出来ていった。
――収録曲中、最初につくられたのは荒内くんが作曲を担当した「魚の骨 鳥の羽根」ですよね。
荒内 そうです。
――イントロダクションの「Modern Steps」に続く2曲目ですが、この曲の冒頭が『POLY LIFE MULTI SOUL』での音楽性の変化を象徴しているように思いました。パーカッションと男女混声のコーラスで始まって、シンセがグワーンと入ってきて……。
髙城 確かに。
――アフロ・ポップを思わせもしますが、ただ、アルバムを通して様々なリズムにアプローチしていますね。『POLY LIFE MULTI SOUL』制作の発端は、やはり、「魚の骨 鳥の羽根」?
荒内 はい。2016年の夏にデモをつくって。
――同年11月から12月にかけて新編成でのツアー<MODERN STEPS TOUR>を行いましたが、この曲もそこで初披露されています。
荒内 夏には小田(朋美)ちゃん、角(銅真美)ちゃん、(古川)麦ちゃんが入ることが決まってたんで、そのメンバーを想定してつくった初めての曲でもあります。
――ツアーではまだタイトルがついていなくて、「あの、リズムが複雑な曲」みたいな感じで話題になりました。荒内くんがエゴサーチをしたら「試されているんじゃないか」「リスナーに対する挑戦か?」みたいな感想も出てきたと。しかし、レコーディングされたヴァージョンを聴くとそこまで複雑だと思わないひとが多いかもしれない。
荒内 今回、アルバムをつくってる時にいちばん気を使ったのが、やっぱり、難しく聴こえさせないっていうか、「難しいことをやってます」っていうプレゼンは絶対にしたくなくて。車で言ったらエンジンの構造は複雑なんだけど、単純に乗り心地が良いみたいな感じが理想。
あるいは、こういう曲って、練習が足りないと複雑に聴こえたりするんですよね。アルバムのヴァージョンは、ツアーの後、ライヴを積み重ねていって馴染んだところで、しっかりと録ったから、むしろ、デモの状態に近くなった。要するにパソコンできっちりクォンタイズしてる状態に近いんで、当初のやりたかった、見せたかった形っていうのはこっち。
あと、ライヴをやってる時に、自分の目の前にダンスが上手な子がいて、「でも、多分、次のセクションでリズムが変わると動きが止まっちゃうな。この子がちゃんと最後までダンスを踊れるようなアレンジにしたいな」みたいなことはよく考えてました。だったら、もうちょっと踊りやすいアプローチに変えようって感じで調整していったんです。
――MODERN STEPS TOURの後、2016年12月(未発表)と2017年6月(『ユリイカ』2017年8月号所収)にやったインタヴューでは、アルバムに向けたceroの新たなモードは荒内くんが先導しているという話になりましたね。
髙城 はい。『Obscure Ride』が出来たあと、僕としてはわりとぼんやりとした時期が続いて。一方、あらぴーは水面下で動いてたんですね。「魚の骨 鳥の羽根」以外にも、7曲目の「Buzzle Bee Ride」だったりとか10曲目の「Waters」だったりとかのタネになるデモをスタジオに持ってきて、ちょっとだけ再生してくれて。何故か最後までは聴かせてくれないっていう(笑)。でも、「あぁ、あらぴーはヴィジョンがあるんだな。じゃあ、とりあえず、その流れに身を任せてみよう」みたいな感じで、手始めに「魚の骨 鳥の羽根」を練習しだした。だから、今回のアルバムの発起人というかプレゼンテーションはあらぴーが担ってくれたと言えますね。
――荒内くんは「2016年は勉強の年だった」と振り返っていました。まずは、リズムについて歴史や楽理を独学で研究したと。
荒内 その後、コードについても勉強し直しました。といっても、専門学校の熱心な1年生といった程度だと思いますが。
――『Obscure Ride』までのceroは、エキゾチカだったりブラック・ミュージックだったり、様々な音楽に影響を受けてアレンジが変わっていったけれど、コードに関してはいわゆる邦楽の範疇に留まっていた、そこを越えたいと言っていました。
荒内 そうですね。今回、リズムが変わったと思うひとが多いかもしれないけど、実はコードの方が凝ってるんです。
髙城 まずはあらぴーがそういったデモを幾つか出してきたんですが、僕としては、曲の台座になってる理論みたいなものを簡単にでも把握しておかないとそのモードに乗れないと思って。だから、当初は同じバンドの中にあらぴーがやりたいことを瞬時に理解出来るひとと、全く分からないひとがいる状態だったんですね。例えば、小田ちゃんとかみっちゃん(光永渉)はツーカーで、あらぴーと「このリズムはこうだよね」「ああだよね」と話してるわけです。一方、僕はそれをじっと聞いて、家に帰ったら検索してみたり。「4拍3連って言ってたなあ」みたいな。
――まずは創造性というよりも知的好奇心に突き動かされていったわけですね。
髙城 MODERN STEPS TOURの時なんかは打ち上げでも音楽理論の話をずっとしてましたからね。真面目か! っていう。
荒内 いつものようにエロ話はせず。
髙城 いや、してたけど(笑)。でも、小田ちゃんが酔っ払って、「心臓の音は3拍子なんだよね!」とか言い出したりして。
――エモいですね。
髙城 その時、僕は勉強モードだから、いちいち、「なるほど! 〝心臓の音は3拍子〟……と」ってメモして。そうしたら、小田ちゃんが「でも、もっと言えば5拍子なんだよね」と言って、「ええっ!?」みたいな。そんな感じで、僕も最初は頭でっかちというか、曲を聴いても、一生懸命、カウントばっかりしてました。
――それが、段々と身体で理解出来るようになった?
髙城 でも、結局、あらぴーの曲で歌詞を書かせてもらったことが良い導入になりましたね。複雑なリズムに対してどう言葉を乗せていくかという。そこで普通にポエムを書いただけだと、演奏はBGMになってしまうわけですから。
――『Obscure Ride』のインタヴューでは、作詞に関して「まずは譜割りを考えずに歌詞を書いて、そこからメロディをつくる」「歌詞とコード進行が出来たら、ラッパーみたいにデモのトラックを何回も何回も再生して、その上で歌詞を呟いてみて、段々とメロディが生まれてきたら、その時点で録る」と言っていました。
髙城 今回、あらぴーからはデモをメロディの縛りがあまりない状態で渡してもらったので、メロディと歌詞を同時につくっていきましたね。
――荒内くんが〝Compose〟、髙城くんが〝Lyrics〟を担当した「魚の骨 鳥の羽根」「Buzzle Bee Ride」「Waters」に関しては、〝Melody Compose〟という形でふたりの名前が書かれていますね。
髙城 そうそう。だから、制約があるといえばある、ないといえばないような感じで。ただ、印象的だったのは、リズムやコードによって選ばされる言葉が変わってくるんですよ。今まで選んでた言葉がハマらなくなるし、逆に、書きながら自分が思いもよらない景色みたいなものが浮かび上がってきたり。それがこのアルバムの世界に自分が入っていくきっかけになりました。
そして、あらぴーがやりたいことだったり、アルバムの方向性だったりが何となく分かってきたところで、じゃあ、その台座の上で自分なりに曲をつくろうということで取り掛かったが「TWNKL」。構想としては、ちょっとレゲエ・マナーというかステッパーみたいなリズムに、複雑な譜割の歌詞を乗せてみようと。
それと、僕の中でトライアルとして重要だったのは「ベッテン・フォールズ」。あの曲が出来たことで肩の力が抜けて。以降は、リズムっていうコンセプトに寄り過ぎるのも良くないと思って、バランスを取るような感じで、自分のもともとのフィールドというか、得意とする、「薄闇の花」や「Double Exposure」みたいな曲を書かせてもらいました。
――橋本くんは、今回のアルバムの制作にあたってどんなことを考えていましたか? 前述のインタヴューでは、「Orphans」のようなメロウな路線をあえて封印して、Logicでサンプリングを試みたり、ブラジルやタイの音楽を研究していると言っていました。
橋本 僕もそのインタヴューの頃は、全然、方向性が定まってなかったんです。とりあえず、あらぴーの後を追ってリズムの森に入って、色々と試してみたものの、結局、変わったリズムの曲をつくると言っても必然性が必要というか……抽象的な表現になりますけど、パッションみたいなものがないとダメなんだなってことに気付いて。1回、森から出たんです。
――『POLY LIFE MULTI SOUL』では、「溯行」とインタールードの「夜になると鮭は」という2曲で作曲を担当していますが、前者は何処となくブラジリアンな、後者はグリッチーなビートの上でサンプリングしたピアノがループする、異なったタイプです。
橋本 「夜になると鮭は」のトラックは、迷いの森の中にいた頃につくったものですね(笑)。そこから、唯一、持ち帰ってきた成果。「溯行」は、曲自体は前からあったもので。
髙城 だから、僕にしてもそうだったんですけど、曲をつくる際に、あらぴーの方向性に合わせてつくろうっていう動機だとやっぱり弱いんですよね。はしもっちゃんの「溯行」はその状態から抜けて出来た曲だから良かったと思う。
――『Obscure Ride』はブラック・ミュージックからの影響を如何に消化するかということに取り組んだアルバムで、あるいは、EP『街の報せ』はその延長線上で打ち込みと生演奏の融合を試みていましたよね。背景には、近年、DJをやったり、クラブ・イベントに出演する機会が増える中でダンス・ミュージックに刺激を受けたり、柳樂光隆さんが『Jazz The New Chapter』で紹介してきたような現行のジャズをリスナーとして掘り下げたことがあったと思うんですけど、『POLY LIFE MULTI SOUL』に関して言うと、様々な要素が絡み合っていて、最早、何かのジャンルやムーヴメントを翻訳するというやり方ではなくなってきているなと。
髙城 MODERN STEPS TOUR以降によく言ってたのは、〝cero〟っていう存在自体にインスパイアされてるっていうか、今のライヴの編成にこそ刺激を与えてもらった感じはありますね。
荒内 『Obscure Ride』で影響を受けてた音楽に関して言えば、アルバムを出した2015年の春ぐらいにCD・ショップに行った時のことが印象に残ってるんです。ちょうど、(ロバート・)グラスパーのフォロワーがヨーロッパから出てきた時期で。視聴して、「あ、良いから買おうかな」と思ってキープしつつまた別のものを視聴したら、「あれ、さっきのと大差ねぇな」と思って、結局、どっちも買わなかったという。「これ、みんな一緒じゃん」って。さらに、こうやってフォロワーとして活動していくことってどうなんだろうと考えちゃったんです。
――それは、当時のceroにも重なったということ?
荒内 そう。ずっと後追いなのは嫌だなと思って。『Obscure Ride』は特にそういうアルバムだったから。
――D’Angelo『Voodoo』のオープニングをコピーするように始まることが象徴するように、リスナーとしてブラック・ミュージックに夢中になっていたわけでしょう?
荒内 ただ、実際に『Obscure Ride』をグラスパーとか、ハイエイタス・カイヨーテとか、ジ・インターネットに渡したことがあって。「聞いて下さい」って。で、アルバムの出来には自信があったのに、影響を受けた当事者に渡すとなると、自分が若干、気後れしてることに気付いてしまって。それだったら、ちゃんと彼ら彼女らに自信を持って渡せるものをつくりたいなと思ったんです。
そもそも、さっき言ったようなグラスパーのフォロワーって、ビートものを参考にして打ち込みを生演奏に置き換えるってことをやってるわけだけど、はっきり言って視野が狭いなと。もちろんそういうものは好きなんですが。一方で、自分たちの興味はブラジルやアフリカにも向かっていたから、それらを研究しつつも、未来のことを考えてつくったら面白いんじゃないかと。だから、今回はいわゆるフォロワー的なものではないふうに聴こえるのかもしれない。
――よりハイブリッドになったと。
髙城 『Obscure Ride』の頃の自分たちもそこにいたわけですけど、そういう、近年のジャズの盛り上がりって、最後の音楽的潮流なんじゃないかって気がするんです。音楽には今まで色々なウェーブがあったわけじゃないですか。
――ニューウェーブだったり。
髙城 ノーウェーヴだったり。
――チルウェーヴだったり、ヴェイパーウェーブだったり。
髙城 ウェーヴ縛りじゃなくてもいいんだけど(笑)。ヒップホップだってそうだし。才能があるひとが現れて、それに追随するひとが現れて、ひとつのカテゴリーが出来ていくっていう現象がこれまで繰り返されて。やがて、それが細分化していったり、再評価されたり、再評価されたものがまた再評価されたりっていうふうに、影響の受け方が複雑になってきてると思うんです。
グラスパーは凄い才能だからフォロワーをたくさん生んだけど、参照先が幾らでもある時代においては、ビュッフェ形式で色々な要素を集めて、自分のプレートをつくるっていうやり方が自然なんじゃないかと。
――今でもムーヴメントは、日々、生まれていると思うんですけど、ceroのバンドの段階として、あるいは皆の年齢として、何かひとつのムーヴメントに熱を上げ、翻訳を試み、みたいな感じではなくなってきているのかもしれない。単純に言うと成熟したというか。
髙城 確かに、そうとも言えるかも。でも、それってかつてのceroがやってきたことでもあるんだけど。まさに、『WORLD RECORD』とか『My Lost City』とかってそういうアルバムだったから。世界中、古今東西の音楽を切り貼りしてめちゃくちゃ雑多なものをつくるっていう。その意味では原点回帰してるのかな。
――歌詞もある種の成熟というか、これまでのように明確な物語に沿ったものではなく抽象化されているように思いました。
髙城 さっきもそういう話になりましたけど、言葉と音楽の関係が、どっちが優位に立ってるかで在り方が変わってきますよね。例えばフォーク……まぁ、そうじゃないフォークもいっぱいあるとして、言葉の方が優位に立つ場合、音楽はあくまでもポエムのBGM、バックグラウンド・ミュージックになる。
――ラップもトラックを差し替えたりするのでそうと言えるかもしれない。
髙城 で、逆に音楽の方が優位に立つ場合、言葉は非言語になるか、ミニマルな……コーネリアスみたいに、ひと言ひと言を音のように扱うか。もしくは日本でも音楽に即すんだったら英語の方が合うから、そうするとか。 じゃあ、言葉と音楽、どちらもイニシアティヴを持ってるものがあるのかと考えると、それはわらべ歌なんじゃないか。「あんたがたどこさ/肥後さ/肥後どこさ」(「肥後手まり唄」)って変拍子ですけど、言葉の区切りがリズムを生んでるので言葉が優位なのかというと、言葉と音楽がイコールだとも言える。それに近いものをつくりたいという思いはあったかな。
――いま話を聞きながら思い出したんですけど、イントロダクションの「Modern Steps」に出てくる「かわわかれわだれ」っていうフレーズが……。
髙城 まさにそれなんです。「かわわかれ(川は枯れ)」と「かれはだれ(彼は誰)」と「だれかわわかれ(誰かは別れ)」っていう言葉がポリリズミックにループするっていう。
――このフレーズってアルバムで繰り返し出てきますよね?
髙城 出てきます。8曲目の「Duble Exposure」と、最後の「Poly Life Multi Soul」でも。それはふと思いついたフレーズなんですけど、言葉遊びでありつつ、言いたいこともちゃんと言えてる。それって目指すところだなと。 『POLY LIFE MULTI SOUL』の歌詞は全体的にそういう感じですね。『Obscure Ride』でやったストーリー・テーリングは自分が得意とするところだから……その後、人に詞を提供する機会が結構ありましたけど、(古川)麦ちゃんとか、冨田ラボさんとか、一十三十一さんとか。そういう時は筆が乗るストーリー・テーリングをガンガンやって、「髙城印」みたいなことにしてる。一方、ceroでは、やっぱり新しいことに挑戦したかったというか、今回、もう一段階進んで、音楽的な言葉を書きたいなと思って取り組んだので、すごく勉強になりましたね。
――今回のアルバムの歌詞からもある種の物語が浮かび上がってきますけど、『WORLD RECORD』から『Obscure Ride』までのキーワードだった〝パラレル・ワールド〟のような分かりやすいものとは違うなと。
髙城 それは、やっぱりさっき言ったように「言葉を選ばされてる」ような感覚からふと出てきたのが〝川〟っていうワードで。
――「歌謡曲的な構造を持っていない曲には、男女が出会ってどうこうみたいないわゆる歌謡曲的な歌詞は到底乗らなくて」「必然的に描くものが〝人〟じゃなくなって、モチーフが水だったり、自然だったり」「たとえば〝3月の水〟(アントニオ・カルロス・ジョビン)のような、もっと現代詩的なものになっていく」と言っていましたよね。
髙城 いま思うとターニング・ポイントになったのが『Obscure Ride』の「Wayang Park Banquet」なのかな。あそこでは、こっち側の世界からあっち側の世界へ跨ぐっていうイメージでポリリズムを使っていて。その上で、言葉も跨ぐ感覚を描けないかトライした。『POLY LIFE MULTI SOUL』はそれが深まってるっていうか、ボーダーで遊ぶ、境界線で遊ぶっていうイメージですね。
だから、舞台としては『Obscure Ride』に近いんだけど、あれが生きてる世界から死んでる世界にフェードアウトしていく話だとして、こっち(『POLY LIFE MULTI SOUL』)の方は逆に、死んでる世界から生きてる世界にギュワーッと出てくる、子供が生まれてくるみたいな、強い矢印というか、ハードな道のりを描いてるなあって途中から気付き始めて。それでいて、川を越えるっていうより川で遊んじゃうみたいな。ボーダーを行ったり来たりしながら、そこを遊び場にするっていう発想が面白いと思って進めて行きましたね。……おれ、なに言ってるんだろう(笑)。
――(笑)。その辺りのことはもう少し話を聞きながら咀嚼していければと。橋本くんはどうでしょう? 髙城くんのように、荒内くんに引っ張られながら、徐々にアルバムの世界観を把握していったと思うのですが。
橋本 未だに全体像は分からないんですよ。さらに最初の頃は本当に何も分からなかったから、皆が出してくる曲を受ける形で自分でもとりあえずつくってみて、「あ、これじゃないんだ」「じゃあ、こんなのはどうかな」って段々と的を絞っていく作業をやっていった感じですね。
――例えば、8曲目の「Duble Exposure」は「Summer Soul」の延長でつくられた楽曲だと言えると思うんですが。
荒内 ソウル歌謡的ですよね。
――アルバム全体として、そういう方向へ進むという選択肢もあったわけじゃないですか。
髙城 あー、確かに。
――売れるために。
荒内 ははは!
――いや、このアルバムが売れないわけじゃないですけど、「Orphans」や「Summer Soul」で上がったポップ・バンドとしての地位を確立することも出来たのに、むしろ、険しい道を選んだというか。
荒内 険しいですよねえ。
髙城 本当にそう。だから、あらぴーが「魚の骨 鳥の羽根」のデモを持ってきた時に、「これ、自分のソロに取っておかなくていいのかな?」って思いましたもん。何というか、「もったいないんじゃない?」って。
荒内 「こんな訳の分からないこと自分でやれよ」って?(笑)
――荒内くんとしては、「魚の骨 鳥の羽根」のような音楽が今いちばんやりたいことであり、目下のプロジェクトがceroのアルバムだから、そこでやるのが自然だったというところでしょうか。
荒内 そうですね。基本的にアイデアは温めておかないタイプですね、思いついたら新鮮なうちに出しちゃう。
――先程も言っていたように、その音楽性自体がceroの今の編成に触発されたものだということもあると思うんですが。
荒内 もちろんそう。あとは単純に、個人的な欲求ですよね。『Obscure Ride』をつくった時も、ああいういわゆるブラック・ミュージック・マナーのポップスが日本では少なかったっていう。リスナーとしてそういうものを聴きたかったし、そういうライヴでドリンク片手にゆらゆらとしたかった。だから、やってみた。そうしたら、需要はめちゃめちゃあったっていうことが発覚して。実際、そういうポップスがいっぱい出てきましたよね。むしろ、今は供給過多だと思うんですよ。リスナーとしてもお腹いっぱいじゃないの? って。
――それは、戦略的な話にも聞こえるけど、創作の発端に、リスナーとしての、音楽好きとしての自分がいるということですかね。
荒内 それもあるし、『My Lost City』が出た後、熊本でライヴをやったじゃないですか。
髙城 おれがライヴ中に酔い潰れた時?(笑)
荒内 そのリベンジでもう1回、やった時(笑)。
――2014年5月に坂口恭平がNAVAROで主催した「まぼろし」というイベントですね。
荒内 そうそう。あの時のライヴは本当に異様な熱気があって。客も「ヤバいヤバい!」みたいな感じでずっと叫んでて。それがいまだに忘れられないんです。『My Lost City』を出した辺りのライヴってそういうことが多くて。
――3.11から間もない頃の雰囲気も相まっていたのかもしれない。
荒内 とにかく、みんな汗だくだった。で、「オレ、実はそっちの方が好きだな」と思ったんです。ただ、いまそういう音楽っていわゆるロック以外ないなと。だから、ジャズやR&B、ヒップホップの流れを汲みながら暴動みたいなライヴが出来たらっていう個人的な欲求も、『POLY LIFE MULTI SOUL』の背景にはあるんですね。
――確かにトランシーな印象も受けました。
荒内 基本的にはダンス・ミュージックをつくりたかったので。
――その思いが最後の表題曲で爆発するという。それでは、ここからアルバムの収録曲を順に読み解いていくことにしましょうか。
(つづく)