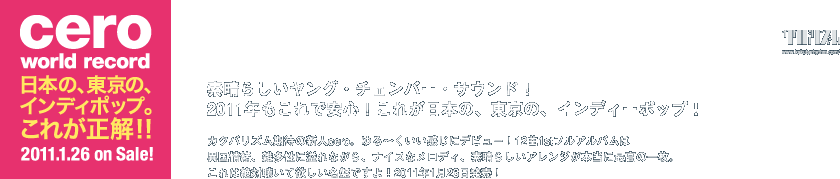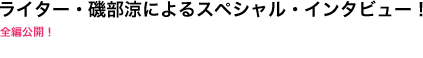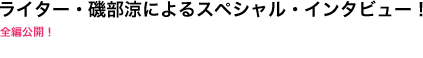

�铐�̂悤�ɖl��͗V�ԁ@�\�\cero�A�g���̂̂��h���

�ʐ^�F�ō�a�V
�@�V�����T�E���h�́A�V�������C�t�E�X�^�C�����琶�܂��B
�@cero�̃t�@�[�X�g�wWORLD RECORD�x�́A�܂�ŁA�s�s��T�����Ă���悤�ȃA���o�����B�{�G�N����|����A�[�g�E���[�N�́A�\�}�͂͂��݂ς��́w�Z���`�����^���ʂ�x���A�F���͗�،c��ƃ��[�����C�_�[�X�́w�̋ʃ{�[�C�x���v���N�������邪�A���A�ɉ��������݁A�ڂ̑O���y���M������ы����čs���l�q���`��������ꂽ���̊G�́A���Ă̓s�s�ւ̃I�}�[�W���ł��Ȃ���A���A���݂̓s�s�̃X�P�b�`�ł��Ȃ��A�����Ŗ��ɂ���Ă���̂́A�����܂ŁA�ˋ�̓s�s���яオ�点��z���͂ł���B���邢�́A����́A�e�B���E�p���E�A���[�ƃq�b�v�z�b�v�ƃ|�X�g�E���b�N���u���R���[�W�������悤�ȁA����̃T�E���h���ے����������̂ł���B
�@�l�I�Șb������Acero�̃t�@�[�X�g�E�C���v���b�V�����́A���̃V�`���G�[�V�������A�^����̓�����ŁA�ޓ����e���̐[�����y�W�c�E�\���iHyogen�j�Ƌ��ɓ���Ȃ�t�ł�̂ɋ��R����������Ƃ������̂������̂������āA����̓o���h�Ƃ��������A�ЂƂ̃��[�h�Ƃ��ċL���Ɏc���Ă���B�G�L�]�`�b�N�ȃt�@���t�@�[���𗁂тȂ���A�Ί�Œʂ蔲����ϋq�����́A���������A�p�������E���[���h�ɋz�����܂�čs���悤�������B�ܘ_�A���̌�̒P�Ƃ̃��C���ŁAcero���̂̃T�E���h�͂܂��Ⴄ���F�N�g���������Ă��邱�Ƃ�m�������A������ǂ������钆�ŁA��͂�A�ޓ�������ł͂��̃��[�h�ƁA���ꂪ�t���E���ċN���郀�[�������g���d�v���Ƃ������Ƃ��m�M�����B
�@cero�́A�\����A�T�|�[�g�E�����o�[��MC.sirafu����Â���u�Ƃꂱ�[�ǁv�A�V���K�[�E�\���O���C�^�[�̂�������O�Y���Ƌ��Ɋɂ₩�ȃR�~���j�e�B���`�����Ă���B���ĂɎʐ^�ƁE��ؗ���N�̌�a��̐��Ƃōs����u�t�W�T�����N�t�F�X�v�A�\�����l�J�斯�z�[���ɃC���h�l�V�A�̉e�G�t�����ق��āA���������z�n�̃v���l�^���E��������āA�s�����C�x���g�B��ې[�����̂͑������A�����̌q���肪�A�����̂�����C���f�B�E�V�[���Ƃ͎�قȂ��Ă���̂́A����������Ӗ��ŃA�i�[�L�[�Ɏ�������ԂȂ̂ɑ��āA�ޓ��́A�]���̒n��Љ�����A�U�������������A�����\��`���悤�Ɂ\�\�܂��ɁA�s�s�̒��ɂ��炽�ȓs�s���яオ�点��悤�ɁA�l�b�g���[�N���Ă���Ƃ��낾�B��́u�t�W�T�����N�t�F�X�v�̃e�[�}�Ɂg�N���[�v���iClopen��Close�{Open�j�h�Ƃ������z�p��A�܂�A�g���Ȃ���J����Ă���h�Ƃ����e�[�}���f���Ă������A����͐e�������A�J���I�ȃV�[���Ȃ̂��B
�@�܂��A���t���[�Y�́Acero�̃T�E���h�ɂ����Ă͂܂邾�낤�B���̋����͉��������A�����Ɍ��������Ƃ��Ă���̂��B�o���h�A���ƂȂ郍���O�E�C���^�����[�����͂����悤�B
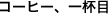
�@�u�q���̍��ɓǂ�ł����A�{���́w��͓S���̖�x�ŁA��l���̃W���o���j�ɏ�����^������̂Ƃ��āA�g�Z���̂悤�Ȑ��h���Ă����t���[�Y���x�X�A�o�ė�����ł��B���A�v���ƁA�y��́g�`�F���h�̂��ƂȂ�ł��傤���ǁA�����̖l�ɂ͕����炸�A�w�Z�����ĉ����낤�A�_�l�̖��O���ȁH�x�Ɗ��Ⴂ���Ă����B�F�Ńo���h����t���悤���ĂȂ������A�ӂƁA�w�g�Z���h���Ă��������x���āA������v���o���āB������A�Ԃ�́A�������gcello�h����Ȃ��āA�K���ȁgcero�h�ɂ�����ł��v�B
�@���鏻���́A�o���h�E�l�[���̗R�����A������������B�b���Ȃ���A�ނ�����Ă��ꂽ����̃R�[�q�[�Ɍ���t����ƁA�ق̂��Ȏ_���ƒ��悢�g�������A��������Ɗ����Ōł܂����g�̂��ق����Ă���A�܂�ŁA�J�t�F�C���ɗn������cero�̉��y���A�̂̒��ŃO���[����t�Ŏn�߂��悤�Ɏv�����B
�@�{��ނ́A��N���̂Ƃ���[���A���邪�������J�w�O�ŕ�e�ƌo�c����J�t�F�^�o�[�uroji�v�ɂčs�����B�����o�[�͂��̌�A�g�ˎ��̃X�^�W�I�ɓ���Ƃ̂��ƂŁA�g�F�̏Ɩ����A�ؒ��̃C���e���A�␔����CD�Ƌ��ɁA�y��P�[�X���I�����W�F�ɐ��߂Ă����B�ޓ��͎n�߂ẴC���^�����[�Ƃ͌����A�ꏊ���z�[���Ƃ������Ƃ������āA�����ă����b�N�X���Ă���悤�Ɍ������B����̃A���o���ɂ͓���Ȃ��������A���C���ł�����݂̊y�ȂɁg������N���[�Y�E�G�L�]�`�J�h�Ƃ����^�C�g�����t�����Ă���悤�ɁAcero��4�l�͊F�A���̃G���A�̏o�g�Ȃ̂��B
�@�u�l�i���鏻���B�p�[�g�̓��H�[�J�����B�ȉ��A������T�j�ƃn�V���������i���{���B�p�[�g�̓M�^�[���B�ȉ��A������H�j���_�㍂�Z�A�A���s�[�i�r���C�B�p�[�g�̓L�[�{�[�h���B�ȉ��A������A�j�ƃ��i�i���q�V�B�p�[�g�̓h�����B�ȉ��A������Y�j���O�鍂�Z�ŁA�S���A84�N�A85�N���܂�̓��w�N�ł��ˁv�iT�j�B�ޓ����o������̂́A���Z��N���̎��ɍ���Ƌ��{���g��ł����A�R�[�q�[�E�t�B���^�[�Ƃ����t���b�p�[�Y�E�M�^�[�E�t�H�����[�̃o���h���A�r�����ς����Ƃ����������������Ƃ����B�u���܂��܁A���C���ɍs���āB�ł��A�ʂɗǂ��Ȃ��āi�j�B�����A����ɉ��y�D�������܂肢�Ȃ������̂ŁA�F�B�ɂȂ肽���ȂƎv���āA�ԍ���l�`�ɐu���āA�d�b���Ă݂���ł��v�iA�j�B�u�����Ȃ�m��Ȃ��ԍ����炩�����ė��āA�K���ɘb���Ă���A�g������CD�����āA�V�тɗ��Ȃ�h���Ă��ƂɂȂ��āA��ׂ��A�r�߂�ꂿ�Ⴂ���˂����āi�j�A�i�ז쐰�b�́j�wHOSONO HOUSE�x�Ƃ������čs�����C������B�����ɒ��ǂ��Ȃ��āA�����A�i���X�ʼn��y�̘b���肵�Ă܂����ˁv�iT�j�B���Ȃ݂ɁA�r���Ɩ����g��ł����o���h�̖��O�͋g�ˎ��Ɏ��݂���X��������������Ƒ��Bcero�ɂƂ��ăJ�t�F�ƃR�[�q�[�͏d�v�ȃA�C�e���̂悤���B����Ȍ𗬂̒��ŁA4�l�͎���Ɉ����t�����Ă����B
�@�ޓ��ɁA���Z����ɍD�����������y�ɂ��Đu���Ă���ƁA�t���b�p�[�Y�E�M�^�[�Ƃ����ŗL�������p�ɂɓo�ꂷ��B4�l�����Z�ɓ��w�����̂�2000�N�B���o���h�̉��U�������10�N�ȏオ�o���Ă����B�u�t���b�p�[�Y�͍D���ł����ˁB�m���Ƀ��A���^�C������Ȃ��̂ŁA�i�o�b�N�O���E���h�ƂȂ鎞��́j���[�h�͒m��Ȃ��ł����ǁA���y���̂��̂��ǂ������B������ƁA�N��̐l�̂��̂�w�L�т��Ē��������͂�������������Ȃ��B����ŁA�̂̎G����ǂ�ł݂�ƁA�ޓ����e�B���E�p���E�A���[�Ƃ��Ɍ��y���Ă��邩��A�`�F�b�N���Ă݂���B���������A�t���b�p�[�Y���̂̓n�V���������ɋ����Ă�������v�iT�j�B�u�l�͎o�������ł����ǁA10��ŁA���傤�ǃt���b�p�[�Y����Ȃ�ł��B���y�͎o�����ɋ����Ă���������̂������ł��ˁv�iH�j�B
�@����A�t���b�p�[�Y�͔ޓ��ɂƂ��ČZ�̂悤�ȑ��݂������B�l�X�ȃW�����������荬�������y�Ȃɂ��Ă��A�����̊y��������ւ��Ȃ��炻����Č����Ă������C���ɂ��Ă��Acero�̉��y�����A������ɔ�ׂĈ��|�I�ɖL���Ȃ̂́A��̐��ォ�瑽���̒m�����p�����Ă��邩�炾�낤�B�u�l�̏ꍇ�́A�S���Ȃ����������y�D����������ł���B������A���Ƃ��ƁA�ƂɃ��R�[�h�����������āA�e�B���E�p���Ȃ��A�Ƃ������āA�����A���ꂩ���Ē��������v�iT�j�B�����āA���̒m���̌p���̓J�^���O�I�Ȃ��݂̂̂Ȃ炸�A���t�Z�p�ɂ��y�ԁB�u����������y�̐搶��������ŁA�q���̍��̓N���V�b�N���Ă܂������A�ƂɃs�A�m����������ŁA����ŗV��ł��邤���ɒe����悤�ɂȂ�܂����ˁv�iA�j�B�u�h�������n�߂��̂́A�ߏ��ɂ������T���W�I������Ă����Ƃ���ŁB�ʂɂ����̓J�g���b�N�ł͂Ȃ���ł����ǁA�h����������Ă݂����Ȃ��Ďv�������ɁA�����ʼn��y�������Ă������Ēm���āA�ʂ��悤�ɂȂ�܂����B���T�A���j�Ƀ~�T�Œ@���Ă܂����ˁB�����������ł���B�w�����Ƃ����Ƃ��Ȃ����A�_�l�͌��Ă��ł���x�Ƃ��{��ꂽ��i�j�v�iY�j�B�u���܁A���i�̘b���Ă��ċh���������ǁA�l���M�^�[�������Ă�������̂������Ȃ�ł���v�iH�j�B�u���[�A�m�炸�ɃZ�b�V�������Ă��烄�o���ˁi�j�B�^�����I�v�iT�j�B
�@���オ�f�₵�A�R�~���j�e�B���@�\���Ȃ��Ȃ������̍��ł́A�Ȃ��Ȃ��A�������P�[�X���ƌ����邾�낤�B�������A�����ŏd�v�Ȃ̂́A�ޓ������b���~�߂��A���̊��ɊÂ��A�I���W�i���e�B�����߂����Ƃł���B�u�ƂɃ��R�[�h���������������Ƃ��A�F����͑A�܂������Č����܂����ǁA�l�ɂƂ��Ă͂ނ���W�����}�ł������ǂˁB�T����т��D���Ă���Ƃ������A���炩���ߑ����Ă��邱�Ƃ̐�]�Ƃ������A������̃R���N�V�������@���Ă��āA�w���������̂���c�c�x�݂����ȁB�����ŒT���Ē����̂ƈႤ����Ȃ��ł����A�����ė��������B������A�����̂��̂ɂȂ�̂͒x�������Ǝv���܂���B�wHOSONO HOUSE�x�ɂ��Ă��A�������̂͑����������ǁA�ӂނӂށA�Ȃ�قǁc�c���āA���̒��̃A�[�J�C���ɓ���Ă������B���ꂪ�{���ɗǂ��Ɗ������āA�����������͍̂ŋ߂̂��Ƃł��v�iT�j�B�����āA4�l����w�ɐi�w����03�N�A��������Ƃ��Ȃ������ė���A���������Ƃ̂Ȃ������g�Z���̂悤�Ȑ��h�ɓ������悤�ɁA���X�Ƀo���h�Fcero�������オ��n�߂�B�u����Ȋ����ŁA���Z�̎��ɂ���Ă��o���h�͐^�������肾��������A�������U�A���Z�b�g���āA���������̉��y�����낤���Ă������ƂɂȂ�����ł��v�iT�j�B

�ʐ^�F�ō�a�V
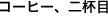
�@03�N�Acero�͌������ꂽ�B�u�F�A�ʁX�ɐi�w����……�Ⴆ�A�l�͓��|�ŁA�����ł������E�����i�J�����}���̗�ؗ���N�j�Ƃ��A��Ɍq����F�B�͂�������o������ł����ǁA����ς�A���y�̎�������̂͂���4�l�A�Ƃ���������������ł���ˁv�iT�j�B�������A�����̃����o�[�͍���^�r���^����3�l�B���{�́A���݂܂ő����\���E���j�b�g���W�I���}�V�[���̑O�g�ƂȂ�Big West Good Three�Ƃ��Ċ������Ă������߁A�s�Q���ƂȂ����B�u�l�ƃn�V���������ŁA�R�[�q�[�E�t�B���^�[�̌�Acue���Ă����A�����悤�Ƀt���b�p�[�Y�E�t�H�����[�̃o���h���������A�n�V����������BWGT��g�B����́A���ɃW�I���}�V�[���ɒʂ��鉹�y���ł����v�iT�j�u���Z���̃��C���E�C�x���g�ŁA�قƂ�ǂ��p���N�E�o���h�Ȃ̂ɁA�ЂƑg�����z�[���E�Z�N�V���������ċh�����܂�������B������A�X�J�R�A����Ȃ��ă\�t�g�E���b�N�������Ă����v�iA�j�u����A����̎��A�l�����������t�w���ɓ����ăN�����l�b�g������Ă���ŁA����Ɋǂ��o����F�B������������ł���v�iH�j�u�n�V���������͋��ʂ��Ă�B����ɔ�ׂāAcero�͂������s�����肱�����s������A�E���E�����Ă銴���v�iT�j�B
�@�����āA�o���h�������I�Ɏn������̂́A���炭�āA���N�̂��Ƃł���B�u�����͂������̂́A���ꂼ��̐V�������Z�����āA�قƂ�NJ������Ă��Ȃ�������ł��B����ŁA1�N�ԁA���y���x��ŁA�F�X�Ƌz�����āA�����ĊJ���ĂȂ������́A�w�ǂ�����������V�������Ƃ�肽���ˁx���āA���R�ƁA�����|�b�v�E�\���O����Ȃ�……3�s�[�X�̃A���T���u������Ȃ��Ƃ����ڎw���Ă��܂����ˁB�Ƃɂ����ʼn_�ɁA�V�����Ǝv�����Ƃ������Ă��������v�iT�j�B���Ȃ݂ɁA���{�̃W�I���}�V�[�����n�߁A�\���E���[�N�ɂ��ϋɓI��cero�����A���̊����͉��y�ȊO�ɂ��y�сA�Ⴆ�A���́A���㗴�w�̂��N�W���x�̕\������|���铙�A�V�i�C�s�̃C���X�g���[�^�[�Ƃ��Ē��ڂ���Ă���B������cero�ɂ��Ă��A�@���ɂ�"�A�[�g�E�X�N�[���E�o���h"�Ƃ�������������Ă����悤�ŁA���̃N���[�v���Ȍ��J�����̏�́A�Ƃ���Ⴂ�|�p�ƒB���W���C�x���g�������B�u�l�̒��w�����ォ��̗F�B�ŁA�g���i���R�m�i�j���Ă����A�̂���Z���X���ǂ��z�����āB�ނ�ICU�i���ۊ����w�t�����Z�j�ɓ����āA�i���̌�A�o���h���\����g�ނ��ƂɂȂ�Ð�j�������Ƃ��A���Z�ŏo������ʔ����l�B��F�X�ƏЉ�Ă���Ă���ł����ǁA�������A�g�ˎ��́�bar drop���Ł�Home �� Away�����Ă����C�x���g���n�߂���ł��B�����ɁA�قږ���o��悤�ɂȂ����̂��Acero�̖{�i�I�ȃX�^�[�g�v�iT�j�u�m���A�C�x���g���̂�03�N����n�߂āA�ŏ��͍���N�ƃ��i��2�l�������̂��A04�N����cero�ŏo��悤�ɂȂ�����Ȃ��������ȁv�iA�j�u�W�I���}�V�[�����o�Ă܂����ˁB��drop�����ď������n�R�Ȃ̂ɁA�z�[���E�Z�N�V�������Ă�ŁA������A��l���ŁB�t�ɒe�������������B�R�[���X��MTR�ɓ���āA"��^�����̂܂����ė��܂���"�݂����ȁv�iH�j�u��Home �� Away����cero�̎n�܂�ł����������ǁA�����Œm�荇�����l�����ƃZ�b�V����������̂��y����������ł���ˁB�i�Ð씞�̓����Y�p��w�̓������ŁA�\���̔��N�l�̂ЂƂ�ł��鍲���j���ƌN�Ə��߂Ęb�����̂����������B���̍��A�ނ̓��H�C�X�E�p�t�H�[�}���X������Ă��B��́A�I���ƃ��i�Ɣ������Ń|�X�^�[�Y�A���ƌN�Ɣ�������DOGEY���ăo���h��g��A������W���J������……�����������藐��銴���́A���̍��A������������������Ȃ��B�����A���Ƃ�����ƈႤ�̂́A�Ⴉ������ŁA�Z�p�I�ɂ͖��n�ł����ǁA"����Ă�낤��"���Ă�����S�I�ȕ��͋C���Y���Ă������Ɓv�iT�j�B
�@�t�@�[�X�g�E�A���o���wWORLD RECORD�x�Ɏ��^����Ă���i���o�[�ŁA�B��A��Home �� Away�������烌�p�[�g���[�ɂ��Ă����̂�"outdoors"���Ƃ����B���Ȃ̑����Ǝ���������A������cero�̎p���z���o����Ƃ������̂��B�u�������ɂ́A�����̕��͋C��������Ǝc���Ă��邩������܂���ˁB���̓C���X�g�����������ł��B���̍��̌��t�Ō����ƃ|�X�g�E���b�N�ɂȂ�̂��ȁH�@�܂��A�y�ȂƂ��Ăǂ������Ƃ��������A�A�e�B�`���[�h�͂����������Ƃ��������ł��ˁv�iT�j�B�o���h�̔w�����������݂̂Ȃ炸�A���̌��cero���ӂ̊����̎w�j�ƂȂ�����Home �� Away���́A��Â̓��R�̃C�^���A���w�����܂������߁A05�N�ɏI�����邱�ƂƂȂ�B���Ȃ݂ɁA�ނ͍��A�r�c���i�̃e�N�j�J���E�`�[���ɎQ�����Ȃ���A���f�B�A�E�A�[�e�B�X�g�Ƃ��Ċ��Ă���B�u�g���͏�Ƀ^�[�~�i���ɂȂ�^�C�v�̓z�ŁA�ނ̂������ŐF��ȏo����������B�C�x���g���I������͎̂c�O�ł������ǁA�����Ŋw���Ƃ����āA�w�����B�ł�낤�x�Ƃ������F�N�g���Ɍ������čs���܂����ˁB�܂��́A�g�ˎ�����䶗����Ƃ��ŁA���ʂɃm���}���Ȃ���o����A�I�[�v����������̍]�m����OPPA-LA���ŁA�W�I���}�V�[���Ƃ������B���̂��炢����A�n�V���������ɂ̓T�|�[�g�ŎQ�����Ă��炤�悤�ɂȂ����v�iT�j�B
�@05�N12��12���A����䶗����ɏo�������ۂ̘^���́w������̃��C��1�x�Ƃ��ĉ���������Ă���B�f�B�X�R�O���t�B�[�̃g�b�v�ɂ�����A�����̑�\��"�ڊo�߂Ă���"��"�o�j�V���O�}�C���h"�����^���ꂽ����DVD-R�́A�����"�����|�b�v�E�\���O����Ȃ��Ƃ���"���o�R���āA������x�A�|�b�v�E�\���O�ɗ����Ԃ�����i�W�ł���B�u����܂ŁA�����I�ɃX���[�E�s�[�X�ł���Ă��̂��A�n�V��������T�|�[�g�œ����ăA�����W�̕����L�������̂ƁA�F��ȃC�x���g�ɏo�Ē��ԈȊO�̎������ӎ����o�������ŁA�܂��A�|�b�v�E�\���O����肽���Ȃ��āA����܂ł̕����]�����A�A���T���u�������t�����тɌX�|���Ă�������ł��v�iT�j�B�܂��A�O�q�����y�Ȃɂ��Ă����������A���삪���o�ŁA�wWORLD RECORD�x�ł��d�v�ȃs�[�X�ƂȂ��Ă���"���d�̖��"�ɂ�����A"���ʂ̉�b�������Ă���"�Ƃ����Z���e���X�̐߉ɏے������悤�ɁA���̍���cero����̓t�B�b�V���}���Y�̉e������������B�u�m���ɁA�A���s�[�ƒm�荇���āA�i���X�ʼn��y�b�����Ă����ہA���ʍ��Ƃ��Đ���オ�����ЂƂ��t�B�b�V���}���Y�ł����v�iT�j�u�l�͍��Z�̎��A������D���������o���h��������Ȃ��v�iA�j�u���傤��cero���n�߂����́APolaris�Ƃ��A�t�B�b�V���}���Y�ȍ~�̃o���h���|�c�|�c�Əo���������ŁA���������Ƃ��Ă��e���������������Ƃ����v��������܂����ˁv�B84�N���܂��cero�̃����o�[�B�́A�����L���̐����Ɠ���ւ��ʼn��y���n�߂����ゾ���A���������̊X����ɂ��Ă��Ă��A�������A�ӔN�̍��������̐ꂽ���̂��Ƃ��f�r���Ă����Ƃ�����A�wWORLD RECORD�x�̓Q�[���ł��v���C����悤�ɗV�щ���Ă��āA���ꂪ�A�M�҂ɂ́A�t�B�b�V���}���Y�̔ᔻ�I�W�J�Ɏv���ĂȂ�Ȃ��̂��B
�@06�N�A���{�����������B���������ĕ\�����{�i�I�Ɋ������J�n�A�ޓ��͓c�[�Ɏ肽�J���I�P�E�{�b�N�X�Ւn�̒n�������X�^�W�I���C�x���g�E�X�y�[�X�ɉ����A�������V�[���̐V���ȋ��_�ƂȂ����B�u�������ł���Ă��C�x���g�ɉ�����iOWKMJ�^���͂���Ȃ���Ȃ��j���o�ĂāA�����ł������i��O�Y�^��OWKMJ�j�N�ɉ�����v�iA�j�ucero���o�Ă���ł����ǁA���ɃA�W�g���ۂ����Ă������A�n�����ɗ��d������Ԃ牺�����Ă��āA����ɒ����U������悤�ɁA��������Ƃ��Ȃ���ҒB���W�܂��ė���l�q�͖ʔ��������ȁB���Ȃ�������ŁA�F�Ŋ������Ń��C��������āB����͉���"�n�܂��Ă銴"�A��������ˁv�iT�j�B

�ʐ^�F�ō�a�V
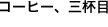
�@ ���̍��A�a���ɕ����Ă�������̕��e���������Ă��܂��B�u�b����́��݂邭���Ń��C��������Ă����ł����ˁB�����C���͊ςɗ��Ă܂������ǁA��drop������̎����I�Ȏ����ł�������B���̌�͕a�C�ɂȂ����������ŁA���������͓n���āA�g�����ǂ��h���Č����Ă����̂́c�c�܂��܂��s���S�Ȃ��̂ł������A�{���͂ǂ��v���Ă������B�ł��A�������Ă���Ă����̂͊m���ł��B�a�����玩���̍D���ȃ��R�[�h�𑗂��Ă��ꂽ��B������A�����Ȃ�A�莆�������Y�����ɁA�iCaptain Beefheart & His Magic Band�́j�wTrout Mask Replica�x���͂��ċh���������Ƃ�����܂����i�j�B���ɂ̓J���^�x���[�E���b�N�Ƃ����D���ŁA�v���O���b�V���E���b�N���o���o���B�����A�����ꏊ���狳�炵�悤�Ƃ��Ă���ł��傤�ˁB�g���������̂������Ƃ���h���āB�����������b�Z�[�W�͉��ƂȂ������Ă܂����B����ŁA�l�́g���x�͂��������̂��������h���ăf���E�e�[�v�𑗂�Ԃ��āB���̂���肪�y���������v�iT�j�B�����āA�e�Ƃ��āA���y���D�Ƃ̐�y�Ƃ��āAcero���T�|�[�g���ė���������̍Ō�̑��蕨���A�ЂƂ̏o��������B�u������́A�l�炪�������f����a������m�荇���ɑ���܂����Ă��݂����Ȃ�ł��B�g���Ƃ��Ȃ����h���Ċ����ŁB��w�����Ƃ����Ă����̂ɏA�E����C�z���Ȃ��������A�S�z��������ł��傤�B����������A���̂�����1����������ă��[�����C�_�[�Y�̗�،c�ꂳ��̎茳�ɓn�����v�iT�j�B����́A���̕����A����̖������̑�ȉ��y�Ƃɑ������Ƃ������Ƃ������̂�������Ȃ��B
�@�g�f���炵�������O�E�`�F���o�[�E�T�E���h���h�Ƃ����A��،c��ɂ��wWORLD RECORD�x�]�i10�N12��15���̃c�C�[�g���j�́A���ɓI�m�ɂ��̃o���h�Ƃ��̃A���o���̓����������\���Ă���B�������A�ŏ��̃Z�b�V�����Ń��R�[�f�B���O���ꂽ�goutdoors�h�������Ɏ��^����Ă��邱�Ƃ����������悤�ɁA�ނ��������̃T�E���h���C���X�p�C�A�����̂��B�u�c�ꂳ��ɒ����Ă�������f���́A�o���h���n�߂Ă������炢�ɂ������ق����̂ŁA������䎩�g���Ⴂ���ƏƂ炵���킹�Ă��ꂽ�̂��͕�����Ȃ��ł����ǁA�g�ǂ��ˁh���Č����ĉ������āv�iT�j�u�g�|�X�g�E�|�X�g�E���b�N�h�Ƃ������Ă���ˁv�iH�j�u�m���ɂ������������������v�iA�j�B2007�N�Acero�͗�،c��Ƌ��ɕ��a���̃X�^�W�I���T�E���h�N���[���ɓ���B�u�c�ꂳ��Ƃ́A�Ƃ���}�l�[�W�����g�̐l��ʂ��ĉ�����肵�Ă���ł����ǁA���̐l���A�g�c�ꂳ����v���f���[�T�[�Ƃ��āA�Ȃ�^�蒼���Ă݂���ǂ����h���Ē�Ă��Ă��ꂽ��ł��B����������A�c�ꂳ�g������A����h���āB����ŁA�]���]���Əo�����āA�g�ڊo�߂Ă����h�Ɓgoutdoors�h��^�������B�c�ꂳ�狳��������Ƃ́c�c�g���R�[�f�B���O�̎��͏o�O�Ń��[���������ȁB�L�т邩��h�Ƃ��H�i�j�v�iT�j�u�Ȃ�قǁc�c�Ǝv�����i�j�v�iH�j�u�Ƃ����̂��A�c�ꂳ��́g�v���f���[�T�[�h���Ċ����ł��̏�ɂ͂��܂������ǁA�g�����A��������I�h�݂����Ȃ��Ƃ͌��킸�ɁA�t�Ɂg�ǂ��������H�h���ėD�����u���Ă���āB������A�l�炪�D������ɂ���������Ȃ̂ɁA�o���オ�������̂��ƌc�ꂳ��̍�i�ɂȂ��Ă���Ă����A�����s�v�c�ȑ̌���������ˁA����́B�g����A���[�����C�_�[�Y���ۂ��I�h���Ă����B����2�Ȃ���ꂽ�̂��A2���ڂ̃f��CD-R�v�iT�j�B����́A�ޓ�����B�ɓ�����āA�g���R�[�f�B���O�h�Ƃ����A�����������苰�낵��������A�o���̂Ȃ����H�ɓ��ݍ��u�Ԃ������B�u���߂Ă̖{�i�I�ȃX�^�W�I�E���[�N��������ł����ǁA�l�͂��̍��A���C�����D������Ȃ������̂������āA�����A�y�����Ďd�����Ȃ������B���T�E���h�E�N���[���͋@�ނ̃����^��������Ă�Ƃ���Ȃ�ŁA�F��Ȋy�킪���������B�X�e�B�[���E�p���Ƃ��v�iH�j�u�m���ɁA���C�����Ă������������āA�g�{���͐F��Ȋy����g���Ă݂������ǂȁh���Ă����v�����A��l�̐l�����̌���Ŕ��U�����Ă������������������ˁB�goutdoors�h�̓r���ŁA�����Ȃ�A�p�[�J�b�V�������{���{�R�{���{�R�����Ă���̂́A�����^���p�ɒu���Ă��������ۂ���������ė��āA�F�Œ@���܂������B�g�����ł���Ȃ��Ƃ�������ł��I�h���Čc�ꂳ��Ɍ�������A�j�R�j�R���Ȃ���g������[�h�݂����ȁB�A���o���ɁA�goutdoors�h�̂��̎��̃e�C�N�����̂܂ܓ��ꂽ�̂́A����������n�܂������������邩��ł��ˁB������������������ŏo������ǂ��Ȃ��Ďv���āA���̌��3�N�Ԃ��炢�͊撣���Ă܂����v�iT�j�B
�@�Ђ���Ƃ�����A���̂܂܍s���Acero�́g���[���E���C�_�[�Y�̎q���B�h�Ƃ��ăf�r���[���Ă�����������Ȃ��B�������A�ޓ��͐e�̊�F���f���D�����ł͂Ȃ��A���ԂƔ閧��n�ɗ��ĘU���Ă͍�����Ă鈫�Y���q�������B�u���ꂩ��A�c�ꂳ��`���ŃR���s�̎d���Ƃ����āA���傭���傭�A�X�^�W�I�ɓ��邱�ƂɂȂ��ł����ǁA�G���W�j�A�̕��ƈꏏ�ɂ��ƁA�����ǂ����̂́A���Ԃ̐���������A�R�~���j�P�[�V��������肭���Ȃ�������A�ǂ����Ă��D���Ȃ悤�ɂ͏o���Ȃ��āB���ꂪ�A�g����ς�A�����B�ł�낤�I�h���Ă����������ɂ͂Ȃ�܂����ˁv�iA�j�Bcero�͗�،c��Ƃ̏o������������ɁA�w�ז쐰�b�\STARANGE SONG BOOK�x�i2008�N�^avex�j�A�w�ɂق�̂����@��j�W�x�i2008�N�^commons�j�A�w���R���s�B�x�i2009�N�^UNIVERSAL�j�ƁA���W���[�E���[�x���̃R���s���[�V�����Ɏ��X�ƎQ�����čs���B�T���猩��Ώ����ȃX�e�b�v�E�A�b�v��������������Ȃ����A�ޓ��͊K�i��������Ԃ��Ă��܂����̂��B�u�}�l�[�W�����g�̐l�������čs�����������ƁA�l�炪�s������������������ƈ������ł���ˁv�iA�j�u�f�������W���[�Ƀv���[�����Ă���Ă����āA������x�̓��X�|���X���������炵�����̂́A�l�炪�X���[��������āB����ŁA�悤�₭������ꂽ�c�c���Ă����ƌꕾ������܂����ǁA�Ώۂ��l���Ȃ��ō�i�������悤�ɂȂ����B�����A�F��ȋ@��������ĉ��������c�ꂳ��ɂ͖{���Ɋ��ӂ��Ă��܂��B�A���o�����������������A�^����ɒ����Ē������v�iT�j�B�����āA�ޓ��͎������g�ƒ��Ԃ̂��߂ɃA���o���̃��R�[�f�B���O���n�߂�B���̎��́A���������wWORLD RECORD�x���ɂ��A�x�X�g�ȑI���������Ƃ����v���Ȃ��̂��B��،c��͓�����āA�u���܂ł̏W�听���ˁv�ƌ������Ƃ����iZINE�u�ǂ�WORLD RECORD�v���j�B����͉��y�I�ȑ��ʂ����łȂ��A�����ɁA�ޓ��̔��w������W��Ă��邱�Ƃ��Ӗ����邾�낤�B
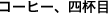
�@���́A�ꖇ�̃��R�[�h�����鏬���s���A���낻��A�I�Ղɋߕt���Ă������A�����ŁA��������肵�悤�B�wWORLD RECORD�x�Ƃ����^�C�g���̒ʂ�A�{���L���ɂ��Ă���̂́A�ޓ������@�C�i���̂悤�ɁA�ړI�n�Ɍ������āA�^�������ł͂Ȃ��A�~��`���Ȃ���i�݁A�����ŁA�j�悪�l�X�ȉ����E�����̂��Ƃ��A���ԂƏo����Ă����o�������炾�B
�@2008�N�Acero�͕\���ƕ��Ԗ��F�i�B�j�A�g�Бz���h���琂��ʂ����Ă���B�u����܂ŁA��Home & Away���Ƃ��\���̃X�^�W�I�Ƃ��A�ЂƂ��W�܂��͂��������ǁA���̓s�x�A���U������Ă������A�F�A�C��ɕY���ĂāA���X�A�o��݂����Ȋ�����������ł���B�ςɂ�ނ����A���̕����ǂ��Ǝv���Ă����B���ꂪ�A�悤�₭�ݕӂɒH�蒅�����ȂƎv�����̂��Бz���Ɖ�������ł��ˁv�iT�j�B�Бz���̏ڍׂȉ��t�������L���ꂽHP�́�Play list���Ƃ����R�[�i�[���Q�Ƃ����Ƃ���A����͕�������������12��13���̂��Ƃ������B�u���k��́�mona records���Ŋ�悳�ꂽ�C�x���g�ɌĂ�āA�g�ǂ����A�����̊������낤�h���čs������c�c���̍��Acero�͏�����mona���̎��ӂł��A���~���́��~�Ձ��̎��ӂł��Ȃ�������Łc�c���A�ł��A�O�֓�Y�������c�c�g�����͓�Y�����Ă����Ȃ��A��A���̕Бz�����Ă����͉̂����낤�H�@�t�p���N�n���ȁH�h�݂����ȁB����������A���C�����ςāA�h�����āB�l����ĕ��i�͊��������āA���C���I������炷���A�����Ⴄ��ł����ǁA���̎��́A�ł��グ�ɂ�����Q��������ł���ˁB�����ŁAMC.sirafu�ɐ����ς炢�Ȃ���g�����[�ō��ł����h���Č������o��������v�iT�j�B���A���E�ɗǂ��o���h�͂������邾�낤�B�������A�ǂ��V�[���͏��Ȃ��B����́A�ǓƂȎ���̔��f�ł�����Bcero�ɐ��E��ς���͂�����Ƃ�����A�ޓ����A�l�Ɛl�̌q����ɂ����A�Ӗ������o���Ă��邩�炾�B�u�����A�Бz�����ǓƂ������Ǝv����ł��B����A�����ł���B�ܘ_�A���Ƃꂱ�[�ǁ��͂��������ǁA�������f���݂����ȁB���ꂪ�A�ʂ̘f���ƌ�M����ꂽ�u�Ԃ����̓���������Ȃ����B�l�B�ɂƂ��Ă��ˁB������A�����������B���A�����̎���ɂ���g�V�[���h�̂悤�Ȃ��̂��Ă������A�g���y������Ă���F�B������h�݂����Ȋ��o���āA����ς�A�Бz���Ƃ̏o����傫���ł��ˁv�iT�j�B
�@���A�茳�Ɂw�o�b�N�x�A�[�h�E�}�K�W�����ʍ��\���W�u�����̉��t�v�x�i�ȉ��A�w�����x�j�Ƒ肳�ꂽ�A�u�b�N���b�g�t����2���gCD-R������B�wWORLD RECORD�x�ɂ��g(I found it)Back Beard�h�Ƃ����C���X�g�D�������^�������߂��Ă��邪�A�u�w�o�b�N�x�A�[�h�`�x�͖l�����|�̒��ԒB�Ƃ���Ă���CD�t��ZINE�ŁA���̋Ȃ̓A���s�[���e�[�}�E�\���O�Ƃ��Ă����Ă��ꂽ��ł��B���̕ӂ̗F�B�W�����y�ɂ������Ă������v�iT�j�B�����āA�w�����x�͂�����R���s���[�V�����Ƃ����`�œW�J�������̂ł���B���s����09�N6��11���B�Q���A�[�e�B�X�g��cero�A�Бz���A��������O�Y�A�O�֓�Y�A�t�@���^�X�^�X�ANRQ���B���^�g���b�N�́A���C���E�n�E�X�A�X�^�W�I�A�����{�݁A����A�l�X�ȏꏊ�ɂ����鉉�t�̃G�A�^��ŁA���̏ꏊ�A���̎��X�̃A���r�G���X�������Ղ�Ƌz�����A09�N�t�̓�����ɂ����t�B�[���h�E���R�[�f�B���O�W�Ƃ����������B�u����i�w�����x�j���A���̕ӂ̏W�܂肪�`�ɂȂ����ŏ���������܂���ˁv�iT�j�B
�@�g�����̉��t�h�́A���Ƃ��ƁA���ꂱ���b����Â���C�x���g�̃^�C�g���i�ȉ��A�R���s�Ƌ�ʂ��ā��������j�ŁA����̃u�b�N���b�g�Ɍf�ڂ��ꂽ���}�ɁA����́g�u�����̉��t�v�Ƃ����̂͒n���o�g�҂ł��鎄�������ŏo��������t�A���w���̂ł��h�ƋL���Ă���B�u�Бz���́A�����O�ɂ��������i����j�Ƃ̏o��������āB�ޏ��́A���̓X�i��roji���j�̂��q��������ł���B���ʂ�OL�߂����Ă����ɁA�d�����I����āA��ꂽ��œۂ݂ɗ��鑶�݂ŁA�����������A������Ƙb������A�g�����D���Łh�g���[�A�l���������Ƃ��Ƃ���Ă��ł���I�h�݂����ɐ���オ���āA���C�����ςɗ��Ă����悤�ɂȂ����B����������A���炭���āg�C�x���g����낤�Ǝv���h���Č����o���āA�n�߂��̂����������i����ڂ�08�N10��23���j�B����ŁA���̔N���ɕБz���ƒm�荇���āA�g���������A�Бz����D��������ςɍs��������������I�h���ėU�����B��������܂��A�������f�����|���|���|���ƌq�����čs�������͂���܂����ˁv�iT�j�B�Бz���́�Play list���ɂ́A���������Ɏn�߂ďo������09�N6��11���t���ŁA�����L����Ă���B�\�\�g�����ɂ͂���Ȃɂ����l�ȃ|�b�v�E�~���[�W�b�N�̂�����������̂��h�I
�@
�@���Ȃ݂ɁA�w�����x�Ɏ��^���ꂽ���鏻���ƃW�I���}�V�[���̃g���b�N�́A09�N4��12���A�������J��roji�� ��ɂ����A��������MC.sirafu�B�Ƃ̃Z�b�V�����ł���B�u06�N�Ɂ�roji�����n�߂���ł����ǁA���������ꂪ�o�����������ŏW�܂�₷���Ȃ����Ƃ����̂͂���B���炿���iMC.sirafu�j����mona���̎��̓��A�����������Ă��ꂽ��ł���v�iT�j�B����܂ŁA�J��Ԃ�����ė����悤�ɁAcero�ɂƂ��ĉ��y����g��h�͂ƂĂ��d�v���B�u��roji���͂���ƃz�[�����o�������Ă���������������ˁB���̏����O����A�m���}���ă��C���E�n�E�X�ł��̂����ɂȂ��āA�o��̂�S���~�߂āA�������N�Ƃ��Ǝl�J�̋斯�Z���^�[�̉��y�����肽�肵�Ă���ł���BMC.sirafu�ɂ��Ă��A�g��h������Ƃ������Ƃɐ����ӎ��I�ŁA���y�̗ǂ��͖ܘ_�A�����������o�������Ă���l�B�ƈꏏ�ɂ�肽���Ƃ����̂͂���܂��v�iA�j�B�ł́A���̏ꏊ����A���y�փt�B�[�h�E�o�b�N�������̂�����̂��낤���H�ucero���āA�ꏊ�ɂ���ăA�����W�������ς����Ⴄ�B�O�����ۂ����Ă����̂������ł����ǁA���~�Ձ��Ŗ{�ԑO�ɂ����Ȃ�A�g�ŋ߁A�����邩��ł��������o���Ȃ��h���Č���ꂽ���ɂ́A�p�b�ƐÂ��Ȋ����ɂ�����Ƃ��A�����������Ƃ��o����̂́A�F��ȏꏊ�ł���ė����̂ƁA������y����ŗ�������Ȃ�Ȃ����ȁB�ǂ����������Ȃ�ł����ǁA�J�`���Ƃ��ĂȂ��A�O�j�����Ƃ����Ƃ���͎c���Ă��܂��v�iT�j�B�����āA����́A�Ґ��ɂ��Ă����l���B�u���̓��ɂ���āA���炿���Ƃ��������N����������B�g�o���h���`�[���h���āA�l�͐̂��猾���Ă܂��B�o���h���Ă����ǓƂȌ`�ł͂Ȃ��A�����Ƒ傫�ȁc�c���̃u���b�N��������Ȃ����ǁA�F��ȃo���h���E�W���E�W������Ă�A�����������͋C�̕����P���Ɋy������Ȃ����Ȃ��āv�iT�j�u���ʁA�����Ȃ��Ă邾�������ǂˁB�ڎw���Ă��Ȃ��B�ǂ����A�����B�̎���̓V�[���Ǝv���Ă�炵�����Ă����̂������Ďn�߂ċC�t���܂�������ˁv�iA�j�B�u�������ˁA�Ӑ}�I����Ȃ��B���̌q����́g��h���A�o���h�����ȑO�܂ők�����ˁB��ӂ̋g�c�i�I���^NRQ�A�O�쌒����DAVID BOWIE�����A���j�N�Ȃ�āA���Z��1��̐�y�����B���сi���^�t�@���^�X�^�X�j�N�����ăA���s�[�̍��Z��2��̐�y�����B���̎킪�g��h�Ɏ����ꂽ���Ƃɂ���ĉԂ��炢�����Ă������v�B�w�����x�́A�O�q�����A����ɂ��g�n���o�g�҂ł��鎄�������ŏo��������t�A���w���h�Ƃ������}�ɂ́A�������A�ȉ��̂悤�Ȓ��߂��������Ă���B�g���y�n�̋�������ʒu�����������Ă�����A�����ł͂Ȃ��ꏊ���܂܂�Ă��܂����A���ꂪ�u�����̉��t�v�Ȃ̂ł��h�ƁB��͂�A���̌��e�̖`���ŏ������ʂ�A�����ł����g�����h�Ƃ́A�����Ƃ����s�s���̂��̂Ƃ��������A����Ƃ���ɎU������g��h�ŘA���I�ɖa����Ă����R�~���j�P�[�V�������w���Ă���̂��B�����āA����̓l�b�g�ȍ~�̃��A���e�B�ł�����B
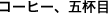
�@�₪�āA����������Бz���Ƃ̌𗬂ƕ��s���ā\�\����A���̌𗬂Ɋ������܂��悤�ɂ��āA�Ə������������m���낤���\�\cero�́A���悢��A�t�@�[�X�g�E�A���o���̃��R�[�f�B���O���J�n����B�u�X�^�[�g��2�N�O�i09�N�j�ɂȂ�̂��ȁH�@6�����炢�������悤�ȁv�iA�j�u�Œ���̋@�ނ������B�Ŕ����āA�g����Ă݂悤���h���āB������ƑO�ɂ��������W���[�̘b�����������A���[�x���Ƃ��������܂��Ă��Ȃ���Ԃł����B�ł��A���̓����̉����c������������ł���ˁB���������������悤�ɁAcero���ă��C�����ɃA�����W��ς����肷�邩��A���낻��A�L�^���Ă��������ȂƁv�iH�j�u���ƁA�g�I�������͂����������Ƃ��������h���Č��Ō������A���Ƃ��Ē�������������₷�����Ȃ��āv�iT�j�u�o���h���������Č��\�o�̂ɂ܂Ƃ܂������̂��Ȃ��������A�g������ӂň�U���Z���āA�V�������Ƃ���肽���ˁh���Ęb�A������ˁB���ꂪ�A����Ȃɒ���������Ƃ͎v��Ȃ������B�ŏ��͕\���ƈꏏ�Ƀ��R���A�����肾��������A��1�N�x�ꂽ�̂��i�j�v�iA�j�B
�@���ہA���R�[�f�B���O�͒����ɓn��A�^�����l�X�ȏꏊ�ōs��ꂽ�B�u�b�N���b�g�̃N���W�b�g�ɂ́gRecorded at �T�E���h�N���[�X�^�W�I�^�g�ˎ��̃X�^�W�I���낢��^������斯�Z���^�[���y���^����|�p�̉Ɓ^�������JRoji�^���������w�Z�^MC.sirafu�X�^�W�I�^�e����h�Ƃ��邪�A���̑f�ނ͊�{�I�ɋ��{�̎���Ń~�b�N�X���ꂽ�B09�N�̏H���ɒ������Ă�������f���̎��_�Ŋy�Ȃ��A�����W���قڌł܂��Ă������̂́A�����������I�Ɍ��サ���̂��~�b�N�X�̋Z�p�ƃZ���X�ł���B�u����Ƃ��ẮA�܂��A�o���h�ŏW�܂��ăx�[�X�ƂȂ鉹��^���āA������e���A�ƂɎ����A���āA�o���o���A���d�^�����āA�Ō�A�͂���������܂Ƃ߂�Ƃ��������ł����ˁv�iT�j�u�Ⴆ�A�h�����̘^����Ȃ���T�肾������ł���B�}�C�N�̈ʒu�Ƃ��A�������āB������A���Ƃ��Ă͓��ꂳ��ĂȂ���ł����ǁA���̕��A�ʔ����f�ނɂȂ��āA��������{�N���~�b�N�X�ŏ�肭�܂Ƃ߂Ă��ꂽ�����ł��ˁv�iY�j�u�|�b�v�E�K�[�h���Ȃ�����C�����}�C�N�ɔ킹����A�g����Ȃ�ł����̂��ȁH�h�Ǝv���A���s���낷��̂��y���������B�ȑO�ƈ���āA�X�^�W�I�̎��Ԃ��C�ɂ��Ȃ��Ŋ��ł��o���邵�B���̕��A�f�ނ��ǂ�ǂ��āA�͂����������͑�ς������Ǝv���v�iT�j�B����A�e�ꏊ�Ř^��ꂽ�w�����x�̂悤�ȃh�L�������g�����E�̒f�Ђ��A�������ɍ����荇���Ȃ���A�t�B�N�V�������ِ��E�ւƐ��܂�ς���Ă������̂��B�u������A�c�ꂳ�g�`�F���o�[�E�T�E���h�h���Č����Ă��ꂽ�̂́A�ق�Ƃɂ����ŁA���̃A���o���͂قڑ�^����ˁv�iH�j
�@�l�X�ȉ����A���o���Ƃ����ЂƂ̐��E�ɂ܂Ƃ܂������Ƃ́A�܂��Acero���ЂƂ̃o���h�Ƃ��Đ��n�������Ƃ��Ӗ������B�ܘ_�A�\���E�A�[�e�B�X�g�̏W�܂�ł���A���̗ւ��O���ւƊɂ��L�����Ă���ޓ��́A�݂����S������悤�Ȃ��Ƃ͂��Ȃ����B�ucero�͒N�����[�_�[�E�V�b�v�����Ƃ��A�ق�ƂȂ��ł��ˁ[�B�D������ɂ���āA���Ƃłǂ����悤���č��銴���v�iT�j�u�����q�̎��v�iH�j�u���C���̃A�����W����肾���������āA�t�@�W�[�ȕ�����������ŁACD�łЂƂ̌`�ɂ܂Ƃ߂Ȃ��Ⴂ���Ȃ��̂��h�������ł��ˁB�F�A�ӌ�������āv�iA�j�u�ǂ����������A���ꂼ���cero�����o���o���Ȃ�ł���ˁB������A���Ƃ��b�Ƃ����ĂāA�����܂����Ȃ�B��̊�����������v�iT�j�u�ł��A���̂܂Ƃ܂�Ȃ����Ă������A�f�b�T���ŗ֊s���������ς��`���āA���ꂪ�ڂ���ƂЂƂ̌`�Ɍ�������Ă����̂�cero���ۂ����ǂˁv�iY�j�u����A�gcero���ۂ��h���Č��t���A�F�A�悭�g����ł����ǁA�����A�o���o���̎��������Ă��āi�j�B�����A�Â�ł܂��Ă��Ȃ�����A�ǂ�������ŕ��݊���āA����Łgcero�h���o�����ł��傤�ˁv�iT�j�B
�@�����ŕ��サ���̂��A�g�G�L�]�`�J�h�Ƃ����e�[�}�������B�����āA�w��͓S���̖�x������p�����A�g��������Ƃ��Ȃ������ė���A���������Ƃ̂Ȃ������Z���̂悤�Ȑ��h�̐��̂��A�gc��contemporary,e��exotica,r��rock,o��orchestra�h�Ƃ����A�N���X�e�B�b�N�͖��ӎ��I�ɖ\�����̂��B�u������A�ӂƁA�g�R���e���|�����[�E�G�L�]�`�J�E���b�N�E�I�[�P�X�g���h���Č�C���ǂ��Ȃ��āA��t���Ŏv���t������ł���ˁB�ł��A��������A��肽�����Ƃ����m�ɂȂ����悤�ȋC������v�iT�j�B�ł́Acero�ɂƂ��āA�g�G�L�]�`�J�h�͉����Ӗ�����̂��B�Ⴆ�A�ז쐰�b�ɂƂ��Ắg�����ł͂Ȃ��ǂ����h�Ƃ������t�Ɠ��`�������낤�B�ނ��Â��ǂ��A�����J�ɓ��ꂽ�̂��A�A���r�G���g�Ɍ��������̂��A���ꂪ�A�g���b�v�E�T�E���h���������炾�B���������A���邪�r���Ə��߂ĉ���Ɏ�ɂ��Ă����̂��wHOSONO HOUSE�x�������B�u�Ӗ��͂ӂ������āA�ЂƂ͂��̂܂܃g���s�J���ȃT�E���h�B�����ЂƂ́A�g�G�L�]�`�J�h�̌ꌹ�ׂĂ݂���Aexdos��exit�݂����ȒP��̓��ɕt���Ă�A���e����Łg�`����O�ցh���Ӗ�����O�u���𖼎����������̂��ƒm���āA���������Ƃ��납��A�L�`�ŃG�L�]�𑨂��Ă��܂��v�iA�j�u����������������A�g����ȃG�L�]�Ȋ����Ƃ������h�Ȋ����Ȃ���h���Ďv���邩������Ȃ����ǁA���������A�O�������čs���A�e�B�e���[�h���Ă������c�c�܂��A��������ٌc�������肷���ł����ǁc�c�����A�A���o���̃^�C�g�����wWORLD RECORD�x���Ăł������o�Ă�̂ɁA�Ō�̋Ȃ��g�����s�h�Ȃ�Łi�j�v�iT�j�B
�@50�N��㔼�ɃA�����J�Ńq�b�g�����G�L�]�e�B�b�N�E�~���[�W�b�N�̏���X���Ƃ��āA�����A���y���n�߂������\�̃X�e���I�E�Z�b�g�ŁA���ۂɗ��s�ɍs���ɂ͒���������Ȃ��Ɛg�j�����ٍ���ɐZ��Ƃ������̂��������B�₪�āA�G�L�]�ł͖O�����炸�A�u�[���̓X�y�[�X�E�~���[�W�b�N�ւƔg�y���Ă����B���ꂩ��50�N��̓��{�A�X�e���I���������Ȃ���ҒB�́A�������AiTunes���痬��Ă���wWORLD RECORD�x�Ŗ������āA�������AiPod�ɗ��Ƃ��ĊO�֏o��A�ڂ̑O�̊X�������ς��čs���̂��B�u�}�[�e�B���E�f�j�[�݂����ȃG�L�]�̕��ƌ����Ă���l�������āA���ǁA�A�����J�l�Ȗ�ŁA�v����ɓ썑���y�̃��v���J�ł���ˁB�l�ɂƂ��āA��������������̂��ۂ����Đ����d�v�ŁA�����̏��������p�������E���[���h���Ă������A�����ǂ������������Ă������́ARPG�̒n�}�������čs���݂����ȏ��������D���ŁB�wWORLD RECORD�x�ɂ��A�e���g�Ƃ��D�ԂƂ��A���o�Ă���L�[���[�h�������ł����ǁA����́A����Ƀ~�j�`���A��z�u���Ă銴�o�Ȃ�ł��B�ł��A�g���[���h���R�[�h�h�Łg�������Ȃ����ڂ����C�Â����낤�^�ƂĂ��Ȃ�����ȃ��R�[�h�̏�Łh���ĉ̂��Ă���ʂ�A�ӂƏ�����グ����A���̊Ԃɂ��A���������̔���ɔz�u����Ă�݂����ȁv�iT�j�u���s�ɏo�����肾�������ǁA���ǁA�n���ɂ���c�c�ł��A���y�̗͂Ŋm���ɉ����܂ōs���Ă����A�݂����Ȋ�������Ȃ��ł����ˁv�iH�j�B����A���̃A���o���̉e���͌����đz���̐��E�ɗ��܂炸�A�\����Бz���Ƃ̏o��̂悤�ɁAcero�Ƃ܂����ʑ��҂��������킹�邱�Ƃ��낤�B�u�c�c�A���o���A����������������Ă�H�v�iT�j�u�����Ē����Ȃ��c�c���ʂɒ����Ă镪�ɂ͋C�t���Ȃ��낤���ǁA�ׂ����������C�ɂȂ�������āv�iH�j�u�I���͌��\�A�����Ă�B���̓x�ɂ����v���̂��c�c�������w�Z���Ă����p�Z�̋����ɁA�\���́i�����j�^�R��������~�`�̃X�e�[�W�������āA�����ňꃖ���Ԃ��炢�F��Ȑl�ƃR���{���[�V������������ہA���ꂪ�I�������ɁAcero�ƕ\���ƁA���ƁA�ӂ��̃o���h���D���Ȑl�B���W�܂��āA�F�ō�����^��������ł��B���̎��̃e�C�N�́A�\���̃A���o���i�w���l�����̏j���x�j�ł��g���Ă��邵�A�wWORLD RECORD�x���Ɓg���̂̂��h��g(I found it)Back Beard�h�A�g�����s�h�ł��g���Ă��āA������ƁA�g����̃A���o���͂����^�邽�߂ɂ������Ȃ��h���āA�������������ł��v�iT�j�B�����A����܂Ől�X�����ѕt���Ă����A�g��������Ƃ��Ȃ������ė���A���������Ƃ̂Ȃ������Z���̂悤�Ȑ��h���A���A�炵�Ă���̂͑��ł��Ȃ��A�ޓ����g�Ȃ̂��B
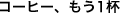
�@�R�[�q�[����t���ފԂɁA�A���o�����������ԂɁA�{��̑f���炵���ɂ��Č�ꂽ��Ǝv���Ă������A�����ƒ������Ă��܂����B��ނ��甼�N�ȏオ�o���A�wWORLD RECORD�x�͕M�҂��ߏ�Ȍ��t���₷�܂ł��Ȃ��A�����ȕ]�����悤�Ɏv���B�������A���̓���U��Ԃ�ƁA���̕��a�����A�܂�ō���̌����p�������E���[���h�̂悤�Ɋ�������ł͂Ȃ����B�����܂ł��Ȃ��A���B�͍��A3.11�ȍ~�̐��E�ɐ����Ă���B�����A���̒��ŁAcero�̉��y�͈ȑO�Ƃ͈�������������悤�ɂȂ����B����́A3��26���̋��s�A��27���̖��É��Ǝn�܂��������[�X�ɔ����c�A�[�ŁA����܂ł͈����ׂ��낤���̂��������C���E�p�t�H�[�}���X���A���Ⴆ��悤��痂����Ȃ����Ƃ��������ł͂Ȃ��B�Ⴆ�A4��2���A�]�k�ɋ����Ȃ���X���̏������Â��X����ʂ�߂��A�a�J��O-nest���Œ������g���d�̖�Ɂh���A���܂łɂȂ��g�ɔ����Ă����̂ɂ͋������ꂽ�B�܂��A4��15���̃��C�����Ō�ɁA������ƋƂɐ�O���邽�߁A�o���h�𗣂�邱�ƂɂȂ����̂����A���̓��A���邪�܂��݂Ȃ���̂����A�I���W�i���E�����o�[�ł͍Ō�ƂȂ�g���d�̖�Ɂh�́g���U��F�B�@�҂������h�Ƃ������C���ɂ͕��Ր����������ƁA��wesred-time������A���ė��Č�����Ȃ̌��t����ۂɎc���Ă���B�m���ɁA���̓������ɁAcero�̉��y�͋��x�𑝂����̂��B����́A�ޓ�������܂ł���Ă������Ɓ\�\�g���d�̖�Ɂh�ɂ���A����Ɉ��p����Ȃ�A�g���ʂ̉�b�����h���邱�Ƃ̑���\�\���A���A���߂Ė���Ă���Ƃ������Ƃł�����B���E�̏I���ɋ�����l�X�ɁA�wWORLD RECORD�x�͐V�������E�𗧂��グ��q���g�������Ǝ��ł����Ă���邾�낤�B1�t�̔��������R�[�q�[�̂悤�ɁB
�i�����j

�ʐ^�F�O�Y�m��
|