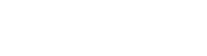
■11. TWNKL 【Composed by 髙城晶平 Lyrics by 髙城晶平】
――いよいよ、アルバムも終盤。11曲目は髙城くんが作詞作曲を手掛けた「TWNKL」。
荒内 おれ、この曲がいちばん好きなんですよ。
髙城 (Part.1で話したように)アルバムの中で最初につくった曲ですね。
――発端となるアイディアとしては、荒内くんが打ち出したリズムというテーマを髙城くんなりに解釈、「ちょっとレゲエ・マナーというかステッパーみたいなリズムに、複雑な譜割の歌詞を乗せてみようと」思ったということでしたが、歌詞は「Double Exposure」と同じように日常描写から始まり、それがカゴから逃げる鳥の視点に変わって、俯瞰描写になっていく。
髙城 〝鳥〟も随所に出てくるんですよね。というか、アルバムを通していろんなメタモルフォーゼをしてて。鳥だったり、蜂だったり。
――そもそも、オープニングの「魚の骨 鳥の羽根」がそういう歌詞です。魚類や鳥類だった頃の記憶が体内で目覚めるという。
髙城 「Double Exporure」でも「鳥の記憶 目覚めた肌」と歌ってる。そのラインの着想としては、人間が興奮したりゾッとした時に鳥肌が立つっていうのは生理現象ですけど、文学的に考えると、鳥だった時の記憶がフラッシュバックしてるんじゃないかと。
――(Part.3で)生と死の間(あわい)としての子供という存在について話しましたけど、子供が魚や鳥といった他の生物との間(あわい)だと考えると、また曲の聴こえ方が違ってきますね。実際、初期の胎児は魚に近いなんていう話もありますが。
髙城 だから、(Part.3で話した「レテの子」の)「忘却(レテ)の水は飲まない」というラインは、鳥の記憶を失くしたくないってことにも繋がってくるっていうか。
――「TWNKL」は最初につくった曲ということもあって、そういったアルバムのテーマの萌芽が見られる。
髙城 2番の「光の川?あれはまぁ Traffic Jamだと思うよ」っていうところで、一応、〝川〟も入ってますし。あと、この歌詞を書いてる時はアナキズムに興味を持ってたんですよね。オザケンさんと電話をしてる時にアナキズムの話になって、(ピョートル・)クロポトキンが気になってると言ったら、「髙城くんからクロポトキンの名前が聴けるなんて!」と驚かれたり。
――学生の頃から友人だという、森元斎さんの著作『アナキズム入門』の刊行記念イベントも<Roji>でやってましたよね。
髙城 そうそう。だから、アナキズム=無政府主義っていう言葉から無茶苦茶で秩序のない状態を思い浮かべてたけど、どうやらそうではないんだなと分かってきたりして。さらにそこに(Part.3で)あらぴーが話してたハウス・ミュージックのユートピアみたいなものを重ねたのかもしれないですね。「やりたい放題 気ままに」とか「そこらじゅうにぶちまける」とかはそういうイメージ。
――曲調としては穏やかなような寂し気なような感じがありますよね。
髙城 「塀の外はどんな感じ?」と訊いてるわけで、主人公は塀の中にいる側なんですよね。だから、幸福な感じもありつつ、結構、閉塞感もあるような気がします。
――カゴから開放した鳥に、自分の思いを託している。
髙城 この時はまだ、(2016年12月発売のEP『街の報せ』収録曲)「ロープウェー」の歌詞を書いた頃を引きずってたのかもしれませんね。
――2015年にお子さんが生まれたわけですが、(Part.2で)「子供のエネルギーって凄いんで、いっときは自分のエネルギーを奪われて、ちょっと鬱っぽくなったりとかしつつ。〝ロープウェー〟にはそれが表われていたりする」と言っていました。
髙城 ちょっと生活に疲れてる感じはあるかも(笑)。
荒内 でも、「ロープウェー」よりは結構オラついてない?
髙城 あはは。空元気みたいな?
荒内 髙城くんの歌詞って繊細なんだけど、端々のニュアンスがオラついてる。ワイルドっていうか。そこのバランス感が良くて。
――〝TWNKL(Twinkle)〟っていうタイトルが喃語みたいものだから、そこからも子供を連想しました。
荒内 ああ、〝Twinkle, Twinkle, Little Star〟ってね。
髙城 確かにこの歌詞を書いた頃、うちの子供が保育園の帰りに自転車の後ろで「きーらーきーらー、ひかーるー」とか歌ってるのを聞いて、いいなぁと思ったことがあったような気がする。で、ぐっときつつ、「あー、酒飲みてえなぁー」みたいな。
荒内 分かる(笑)。
髙城 この曲には子供が生まれたばっかりのお父さんの、「酒飲みてえな」って感じが凄く出てると思う(笑)。
荒内 家庭という塀の中に閉じ込められた?
髙城 急に所帯染みた話になってきたな!
――ロマンチックな曲だと思ってたのに……。
髙城 でも、意外とそんなもんだと思う。
――もともと、髙城くんの歌詞って日常に根差しながら、空想を膨らませていくというタイプが多かったですよね。
髙城 それもあるし、子供が生まれてから、以前の日常が完全に非日常化しちゃったんですよね。パーティでワイワイしたりっていう世界が。
橋本 なるほど……。
髙城 「塀の外は どんなんだい」? はしもっちゃん!
橋本 おれは鳥だったのか(笑)。
髙城 あるいは「Lonesome Ramble Boy」(笑)。
■12. Poly Life Multi Soul 【Composed by 荒内佑 Lyrics by 荒内佑】
――そして、最後の曲。これまでのアルバムの終わり方……後日談っぽい「小旅行」(『WORLD RECORD』)や「わたしのすがた」(『My Lost City』)、バラードの「FALLIN’」(『Obscure Ride』)ともまた違った、ダンス・チューンで幕を閉じます。
荒内 この曲も最初からエンディングに置くことを考えてつくったんです。ただ、これまでしっとりとした終わりが多かったんで、今回はブチアゲて終わりにしようと。
――BPMはぴったり120。そこもコンセプチュアルですよね。
荒内 そうそう、(DJに)ハウスに繋いでもらうっていう前提でつくってる。これね、話すこと多いんです。
――タイトル・トラックですから、込められている意味も多そうですよね。
荒内 角ちゃん(角銅真実)がいつも言ってるんですけど。「このメンバーで一緒に演奏してるのが面白いと!」みたいな。〝と!〟とは言わないけど(笑)、やっぱり、今のceroの、サポート・メンバーを含めて8人からなる社会性が面白いなと。そこから〝Poly Life〟というフレーズを連想したのもあります。
――8人はそれぞれ独立したアーティストでもあるわけですが、そのようなひとたちが人生の一時を共有することに面白さを感じた?
荒内 そうですね。非同期のまま同じ場所にいるっていうか。
――そこから、アルバムの〝(ポリ)リズム〟というテーマにも繋がってくる。
荒内 先程(Part.2、3)から言ってる「音楽性と文学性を混同することが面白い」という話だと、タイトルでは、ポリリズムとかポリフォニーとかこのアルバムの基調となってるところは匂わせつつも、あまり音楽性だけを前面には出したくない。そこで、ceroが置かれてる状況を鑑みると、〝ポリ〟と結び付けるべき言葉はやっぱり〝ライフ〟かなって。さらに、〝マルチ・ソウル〟というフレーズを思い付いて、これだと。
――髙城くんがアルバムに寄せたコメントでは「連なる生、散らばる魂」と訳していました。
髙城 レコーディングが進んで、「アルバム・タイトルはどうしようか?」みたいな話になった時に、あらぴーがパッと「Poly Life Multi Soul」というフレーズを言って、即決でしたね。『Obscure Ride』の時は時間がかかったけど、今回は1発。「そうだよなぁ」っていう。
――楽曲としては、アルバムを通して〝ポリ〟だったり〝マルチ〟だったりという側面を強調していた演奏が、ここでは終盤、4つ打ちによって同期、クライマックスを迎えます。
荒内 ただ、(楽曲としての)「Poly Life Multi Soul」に関しては、このタイトルにも関わらず音楽性に複層的な要素がなかったので、それをどういうふうに表現しようかなと考えた時に、自分で歌詞を書いて、ダブル・ミーニング、トリプル・ミーニング……つまり、〝ポリ〟ミーニングみたいなことをやったら、「音楽性と文学性を混同」することが出来るんじゃないかと。冒頭の「漂う期待 液状の夜に」っていうラインはその試行錯誤の名残りですね。〝期待〟と〝気体〟がかかってる。
ただ、歌詞全体でそういうことは出来なくて、どうしようかなと悩んでた時に、(Part.1で話した)同じフレーズ、同じメロディのリフレインなんだけど、リズムが1拍ずれることによってアクセントが変わり、騙し絵みたいに複数のイメージが浮かぶっていうシステムを思い付いて。で、スタジオに行って、「ここにあてはまるいいフレーズないかな?」って訊いて。
髙城 そこで、皆で頭をひねったんですけど出てこなくて。結局、家に帰って風呂に入ってる時に「かわわかれわだれ」っていうフレーズを思い付いた。
荒内 ほんと、ばっちりなものを考えてくれましたね。
――そこには、「かわわかれ(川は枯れ)」「かれはだれ(彼は誰)」「だれかわわかれ(誰かは別れ)」といった言葉が隠れている。
荒内 あと、〝かわだれ(彼は誰時)〟って明け方の意味だったり。
――結局、このフレーズはアルバムの中で繰り返し使われることになりますが、もともとは、タイトル曲のためにつくった。
荒内 そう。アルバムの最後で川が干上がり、主人公が誰かも分からなくなっていく、みたいなイメージ。(13年のEP)『Yellow Magus』の時、(砂漠をテーマにする上で)参照にしてた白石かずこの「砂族の系譜」って詩があるんですけど、そこに戻った感じもあって。それと、歌詞を書いてる時にちょうど『ルポ 川崎』を読んでたんです。
――確かに、あの本でも〝川〟を日常と非日常を隔てるボーダーとして描きました。
荒内 ただ、(同書の主な舞台となる川崎区臨海部で)いろいろな人種のひとたちが同じ場所に住む中、問題が起きたり、それを乗り越えようとしたりっていう話を読んで、〝Poly Life〟なんて気軽に使えない言葉だなとも思って。このタイトルって、「みんなちがって、みんないい」みたいなお行儀のいいフレーズにも聞こえるじゃないですか。
――あるいは多文化共生みたいな。行政が使いたがるフレーズですけど、現実はそんなに簡単じゃないっていう。
荒内 うん。説教臭く聞こえたら嫌だなと思ったんですけど、アルバムの制作を通して自分たちなりに、複数の人間が非同期のままひとつのものをつくるっていうことの困難さと楽しさを噛み締めたので、使ってもいいのかなって。翻って言えば、『ルポ 川崎』に背中を押されたようなところはありました。
――そういうふうに読んでくれたとは嬉しいです。
荒内 髙城くんからデモが送られてきた時、タイトルが「Double Exposure」(多重露光=別々に写した被写体を1つの写真に重ね合わせるテクニック)だった時も、まだ何もそういう話はしてなかったけど、「ああ、同じことを考えてるっぽいな」「このタイトル使ってもいいかもな」って思いましたね。
――これまでも髙城くんの歌詞は、パラレル・ワールドっていう設定を通して、1人の人間が持つ複数の側面について歌っていたと思うんですけど、今作で、複数の人間がひとつのものを共有するというテーマに拡張されたことから、ceroの成熟を感じました。
荒内 あと、この曲では〝水〟が変化していくっていうモチーフも使っていて。ガルシア・マルケスの『百年の孤独』の冒頭で、ジプシーが村に持ってきた箱を空けるとダイヤモンドがつまっていて驚くんですけど、実は氷だったっていうシーンがあるんですね。それが溶けると単なる水になってしまうように、H2Oには何処かマジック・リアリズム的なところがあって。それがceroの世界観にも通じるなと考えて、1番では気体が液状になり、2番ではアイスキューブ……固体になり、という描写を入れてる。
――ceroの新しい代表曲だと思います。
荒内 おお、本当ですか? まぁ、単純に言えば踊れる曲をつくりたかったっていうことですよね。難しい曲ばっかりやってると、(ceroのライヴの常連で、DJの)みのさん(DJ minoda)とかこいちゃん(SPORTS-KOIDE)とかが楽しんでくれないんじゃないかって。
一同 (笑)。
荒内 あと、showgunnさんとかのことも、頭の片隅にずっとチラついてて。あの人たちがライヴに来て、楽しんでくれなきゃやだなって。
――パーティー・ピープルが。
荒内 そうそう(笑)。ライヴが終わった後、「凄かったよ! じゃっ!」って帰られたらショックじゃないですか。それより、「楽しかったよ!」って言われて、一緒に酒を飲める、そういう曲をつくりたいなと思ってましたね。
――(Part.3で)「ceroでそのままハウスを取り入れると、いわゆる4つ打ちロック的なものになってしまう」のではないかという危惧もあったと言っていましたが、それでもあえて4つ打ちを入れたわけですよね。
荒内 通して聴いてここまで来て、4つ打ちが入ってきた瞬間に「あ、これってダンス・ミュージックのアルバムだったんだ」と気付いてもらいたかったんです。で、また1曲目から再生すると違った聴こえ方をすると思う。今作においてはそういう解決の仕方に落ち着いたっていうことです。
髙城 DJ・プレイにおける〝しごきタイム〟ってあるじゃないですか。クロスリズムとかで簡単には踊れなくて、「どうリズムを取ったらいいんだろう?」って快感に摩擦を感じてる状態というか。まぁ、しごきタイムにはしごきタイムの快楽があるんだけど(笑)。しばらく摩擦に耐えてると、ご褒美みたいにドンドンドンドンって4つ打ちが入ってくる。そうすると、最初から入ってるよりもカタルシスが倍増するでしょう? 同じように、この曲って、疾走感だけじゃなく、後ろに引っ張る力が加わって独特のドライブ感が生まれてると思う。推進力と、それに引っ張られて進んでくものとの間に、ちょうど水上スキーのような遠心力があって。それが四つ打ちになってた時に解き放たれる気持ち良さも生んでる。こういうことって、クロスリズムを理解しなければやれなかった気がするし、シンプルなものの中にある複雑な回路を見つめ直したからこそ、辿り着いた表現だと思う。
荒内 「かわわかれかれはだれ」もここまでの流れがないと出てこなかったフレーズだし、シンプルな構造で新しいceroを表現することが出来たという達成感がありますね。
――こうしてアルバムの流れに沿って話を聞きながら思ったのは、髙城くんが「リズムやコードによって選ばされる言葉が変わってくる」「(荒内が示した新たな方向性によって)必然的に描くものが〝人〟じゃなくなって、モチーフが水だったり、自然だったり」「現代詩的なものになって」いったと言っていましたが、一方で、これまでのceroにあった物語性もまた違った形で表れているなと。
髙城 自分でも、ceroの楽曲がどうしてもストーリー性を帯びてしまうのは何故なんだろうと考えてたんですけど、この間、Twitterで何人かのマンガ家のひとたちがストーリーについてお互いの見解を話し合ってるのを見て凄く面白いなと思ったんです。例えば、高野文子さんがこれまでいろいろなところで発言してるのが、「マンガについて考え過ぎたせいか、ストーリーや登場人物に興味を持てなくなった」みたいなことで。それに対して、島田虎之介さんっていう僕の大好きなマンガ家さんは、「高野さんが言うことは実感出来て、ストーリーや登場人物っていうのはわざとらしい」と言うんですね。「自分はストーリーも登場人物も描くのが楽しいので描くわけだけど、わざとらしさを回避するために色々やったりやらなかったりしてる」と。
――島田虎之介さんは物語というものにこだわりがある作家だというイメージがありました。
髙城 それでもやっぱり、ストーリーを生み出すにあたって凄く苦心してるっていうようなことを言っていて。で、また別のマンガ家さんなんかは、「コマが2つあるだけで時間が発生して、そこにストーリーが出来てしまう。それを逃れようとすると詩になってしまう」みたいなことを。そのやり取りを見て、自分はアルバムをマンガ的につくってるのかもしれないと思ったんです。1曲1曲がコマで、2曲並ぶことでそこにストーリーが発生するというか。多分、そういう思考でつくってきたんだろうなって。
――ただ、今回の物語性はこれまでと違って時間軸に縛れていないような気もするんですよね。
髙城 そうなんですよね。その時間のないストーリーが何なんだろうってことも考えていて。自分はマンガや小説を書こうとして書けなかった人間なので、ストーリーに対する欲求をポップスで満たしてるところもあるでしょうね。一方で、アルバムと言うと、一応は僕たちが決めた曲順で並べますけど、その通りに聴かれるわけではない。さらに、ライヴとなると他のアルバムともシャッフルされて違う物語をつくっていくわけで、それが何より面白いし、マンガや小説には出来ないことで。だから、〝書き換え可能な物語〟っていうものが、ポップスの魅力だなってことはずっと感じてたんです。
荒内 おれも、今回、時間について考えることが多かったですね。これまでのceroが持っていたのはヨーロッパ的な時間感覚というのか、自分が曲を書いたり、物語ることで時間をつくり出すみたいな感覚だったけど、今回は既に存在する時間を自分達で割り直していったっていうか。
――なるほど。ステレオ・タイプかもしれないですけど、ブラック・ミュージックのアーティストに対して、普段の仕草や喋り方からしてグルーヴィーで、演奏や歌唱はその延長線上にあるみたいな言い方がされますよね。常に音楽的時間を生きているという。対して、オーケストラの作曲は時間をいちから構築するイメージ。
荒内 昔のアフリカ音楽を採譜したものを見ると、めちゃくちゃ変拍子で書いてあったりするんですけど、要は音が鳴ってるところを起点として捉えてるから、そういう認識になる。で、その後、研究が進むと、4拍子の中で休符を多用した採譜の仕方に変わる。一定のグルーヴの中で音の抜き差しが行われてるんだっていう認識になったんですね。今回、意識していた時間の流れも後者で、それこそがアフリカ的というか、ダンス・ミュージック的なんじゃないかと思ってました。
――「音楽性と文学性を混同する」ということで言うと、その時間感覚が物語性にも影響を及ぼすわけですよね。
荒内 今回は作曲もモーダルなので、コードを展開させて物語を進めて行くのではなく、環境をデザインしてプレイヤーに好きな音を選んでもらうっていうつくり方。そこに髙城くんが言葉を乗せる上で苦労していたのが、従来の物語構造が合いづらいことで。
髙城 そうか、そういうことだったんだね。
荒内 理論は知らなくても実感として分かるんだなって、密かに感動してたんだけど。
――自分達が物語を生み出すというよりは、もともとある物語を生きるようなつくり方になったのかもしれません。
髙城 だから、コマが並んでるっていうよりはポリになっていて、見方によってはステレオグラムみたいに別の絵が浮かんでくるっていう感じなのかもしれない。
――橋本くんはどうですか? 「自分たちでもまだアルバムの全貌が掴めていない」ということでしたが(リードで書いたように、このインタヴューはミックスが終わった直後、マスタリングの前に行われた)。
橋本 楽しみですね。今日も2人の話に、「そうだったんだ!」と思うことが多かったんですけど、これを踏まえてアルバムを聴くことが。
――ceroはアルバム毎に変わり続けてきたわけですが、先程言ったように今作はバンドにとってある種の成熟の表われなのでしょうか。それとも、いまだ過渡期なのでしょうか。
荒内 どうなんだろう……。
髙城 不思議と、子供に戻ったような感じもあるんですよね。最初、あらぴーがリズムっていう難解なテーマを提示してきて、それを自分なりに理解しながら大人になったような気持ちでいたんですけど、結局、創作の糧は好奇心だったんですよね。だから、振り返ってみると、本当に子供みたいに好奇心に突き動かされながら無邪気につくったという印象。それは、いわゆる初期衝動でつくっていた『WORLD RECORD』とか『My Lost City』の頃ともまた違ったモードなんですが、とにかく、楽しかったです。ハードでしたけど、エンジョイしました。