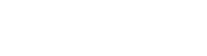
■07. Buzzle Bee Ride 【Composed by 荒内佑 Lyrics by 髙城晶平 Melody composed by 髙城晶平 / 荒内佑】
――ここからアルバムの後半。インタールード「夜になると鮭は」が残したダウナーな雰囲気を、シンセ・ベースとファンク・ビートが掻き分けるように始まる曲。ただ、その後、どんどん展開して、何とも形容し難い曲調になっていきます。
荒内 これは、(オープニングの)「魚の骨 鳥の羽根」と対になるものを、と思ってつくった曲ですね。着想としてあったのは、アフリカに偏在するリズム型。塚田健一さんの『アフリカ音楽の正体』という本によれば、アフリカには1000以上の民族が住んでいて、その中でも共通したリズム・パターンを5つに分類できると。それがラテン音楽で聞かれるクラーベの原型とされておりーーアフリカにはクラーベはないんですが、海を渡ることでリズムが変形していったらしいんですね。だから、そういう流れを人工的につくってみようと考えて、アフリカのリズム型のあるパターンを7拍子に変形させてみた。それが曲中に出てくるカウベルのパターン。さらに、そこにいわゆるアフロ・ビートが混ざってくる展開にしたら面白いんじゃないかと考えたんです。
――ヴァーチャルなリズムなんですね。
荒内 あと、今回の自分の曲は全部そうなんですけど、トライバルなビートにジャジーなコードが乗ってるという。
――近年、アフリカ諸国のポップ・ミュージック/ダンス・ミュージックが注目を集めて、様々なジャンルに取り入れられていますよね。そういった流れには影響を受けていますか?
荒内 好きですけどね。AWESOME TAPES FROM AFRICAとか、JIMI TENORとか。ただ、やっぱり(Part.1でも話したように)それに影響を受け過ぎても後追いになっちゃうので。対して、この曲みたいにファンクっぽいんだけど7拍子だとか、「ベッテン・フォールズ」みたいにロック・イディオムを使ってるんだけど実は5拍子だとか、1拍増えたり減ったりするだけで別ものになるっていうのがリズムに凝る面白さのひとつでもあって。もともとあるリズムを脱臼させたり変形させたりして、新たなリズムを人工的につくるっていう、さっき言ったみたいにヴァーチャルな側面の方が今回は強いかもしれませんね。
――以前のceroのテーマに〝エキゾチシズム(異国情緒)〟がありましたけど、今回はある意味でそうではなくなっているということですかね。「Buzzle Bee Ride」もクラーベやアフロ・ビートを出発点として、無国籍なものになっているわけじゃないですか。
荒内 アイディアの着想としてはアフリカがありますけど、民族音楽をやりたいわけではまったくないですからね。
――タイトルはシンセ・ベースの音から連想したもの?
荒内 架空のアトラクションの名前ですね。タイトルはいちばん最後につけたんですが、制作中に「この曲って遊園地っぽいな」と思ったことがあったんです。スペースマウンテンみたいな。髙城くんの歌詞もそうだし、最初のはしもっちゃんのギターもジェットコースターがガガガガって上がってくところみたいだし、最後の、リズムがダッダッダッとなるのもアトラクションがゴールに着いて止まるところみたいだなって。「魚の骨 鳥の羽根」について(Part.2で)「音楽性と文学性を混同することが面白いんじゃないか」という話をしましたけど、ここでも、対になる曲として同じことを試みたという感じですね。
――橋本くんが(Part.1で)「変わったリズムの曲をつくると言っても必然性が必要」「パッションみたいなものがないとダメ」と言っていましたけど、それが、荒内くんの表現では「音楽性と文学性を混同する」ということになるんですかね。
荒内 最近はリズムに凝ってる人ってたくさんいますけど、ただ、ceroがそれだけを突き詰めて、髙城くんが描いてきた世界観を捨てちゃうのはもったいなさ過ぎる。かと言って、フォークのように言葉に寄り過ぎてもうちららしくないし、そこでお互い(音楽と言葉)が浸食しあうというのは、ceroがリズムに凝る理由になるのかなと。
――なるほど。この曲も「魚の骨 鳥の羽根」と同じように、荒内くんのデモに、髙城くんが歌詞と一部のメロディを上書きしていった感じでしょうか?
髙城 そうですね。最初、デモを聴いた時にフューチャリズムを感じたので、それこそ、SF……『ブレードランナー』みたいな、酸性雨が降りしきるディストピアを浮かべながら歌詞を書いていきました。その時はジェットコースターとかライドするとかっていうイメージはなくて。
荒内 制作しながら、この迫力のあるシンベ(シンセ・ベース)とシリアスな言葉をもうちょっと中和するような要素を入れたいなと思い、乗り物っていうもうひとつのテーマを思い付いたんですよね。あくまでジェットコースターみたいな、エンターテイメントとしての緊張感にしたかった。なので、YouTubeで一般客が撮ったスペースマウンテンの動画を見て、SEをシンセで真似てつくりました。うっすら入ってるアナウンスもスペースマウンテンのものを調べて、それを基本にしてます。「夜になると鮭は」のエンディングに被ってくる形で始まる曲の導入部に、いろいろ入ってますね。
――このアルバムの曲調ってちょっと不穏だったり、物悲しかったりしますけど、リズムが面白いのもあって楽しみながら聴き通せますよね。
髙城 そうそう。ハードな道のりなんだけど、エンジョイしながら進むっていうか、好奇心に突き動かされていくっていうか、ジョイがある感じにしたいなとは考えてましたね。
荒内 髙城くんが言ったフューチャリズムっていうことに関して、いわゆるアフロ・フューチャリズム……アフリカ系アメリカ人がアイデンティティを宇宙とか未来に求めるみたいな思考は、ceroもルーツレス、根無し草だし、そこは初期のエキゾチズムにも近いと思うので、共感するようなところがありますね。
■08. Double Exposure 【Composed by 髙城晶平 Lyrics by 髙城晶平】
――続いて「Double Exposure」。この曲に関しては、最初の方(Part.1)で「「Summer Soul」の延長でつくられた楽曲」ではないかと言ったら、荒内くんも「ソウル歌謡的」と答えていました。リズム・マシンのチープなビートで始まって、シンセの泣きのメロディが入ってきて……。ただ、これもまた後半でがらっと違う曲調にスウィッチしますね。
髙城 僕も、自分の得意とするもの中でも割と歌謡曲的な側面が出た曲だと思ってるんですけど、アイディアの原点としてあったのは歌詞で書いたようなイメージだったかな。
――歌詞はアルバムの中でもいちばん日常的だと言ってもいいかもしれません。そこから別の世界が垣間見えるという、『Obscure Ride』に近い感じ。
髙城 そうですね。「魚の骨 鳥の羽根」も日常生活に違うヴィジョンが這入り込んでくるイメージでしたけど、あそこでは最終的にあっちの世界にワープしちゃう。「Double Exposure」は(Part.1で話したような)ボーダー、境界線で遊んでる状態というか。具体的に言うと、(Part.2で話したような)子供と一緒にしゃがみ込んで街を眺めた時に感じた、現実が〝Double Exposure=多重露光〟(別々に写した被写体を1つの写真に重ね合わせるテクニック)になるようなイメージがまずあって。
――後半のパートでは、付き合いの長い関口将史さんのチェロを始め、田島華乃さんのヴァイオリン、須原杏さんのヴィオラといったストリングスが取り入れられていますね。
髙城 そのパートは録音が始まってから思いついてつくったんですけど、最初はみっちゃんに「余白を残す感じで、適当に叩いて」と言って、僕とはしもっちゃんとでギターのフィードバック・ノイズを入れたりして。そのまま放っておいたところに、録音の終盤、また思い付いてストリングスを入れてもらった。まぁ、言ってみれば〝多重露光〟というイメージを音楽の中でも表現したかったんですね。他の曲に比べたらシンプルな構造ですけど、1曲の中に異なったものが同居してる。
荒内 おれはアルバムの曲が出揃った時、これがいちばんキャッチーだと思ったな。
髙城 へぇ、そうなんだ。
――今回はどの曲もそうだとも言えますが、〝何々っぽい〟とは言い切らせないような捻った感じもありますよね。
髙城 その後半のパートは(Part.2で話したように)「ベッテン・フォールズ」をつくる時に聴いてた、シカゴ音響派の影響が顔を出してるかもしれない。ちょっとジム・オルークさんっぽいというか。
――当初、アルバムの制作は荒内くんが引っ張っていったということでしたが、結局、荒内くん主導が5曲、髙城くん主導が5曲、橋本くん主導が2曲ということで、髙城くんの楽曲の割合も高くなりましたね。
髙城 (Part.1で話したように)最初はあらぴーが考えてることに追いつくので必死って感じでしたけど、リズムに凝った「ベッテン・フォールズ」が出来たことで、後はもうちょっとのびのびとつくってもいいかなっていうか、もう少し言葉にも比重を寄せないとアルバムとしてバランスが悪くなるだろうなと思って。そこから、「薄闇の花」やこの曲がぽんぽんと出来ましたね。
荒内 いやぁ、これはいいよ。ホッとするよね。最後、ちょっと裏切られるけどそこがまたいい。
■09. レテの子 【Composed by 髙城晶平 Lyrics by 髙城晶平】
――次も髙城くんの曲ですが、これはボ・ディドリーのいわゆるジャングル・ビートをベースにしているんですかね。
髙城 ドンダンドン! ドンダダドン! みたいなロッキンというか、オールディーズな……。この曲は、もともと「Aflo Atom」っていう仮タイトルで、(山下達郎の)「アトムの子」が下敷きになってるんです。
――ああ、あの曲もジャングル・ビートですよね。
髙城 でも、あれって他のどこにもない音楽じゃないですか。あのビートの上で、シンセの2コードがループして、ぐんぐん進んでく。前々から達郎さんの中でも凄い特殊な曲だなと思ってたんですけど、ふと、今のceroがやってることにも近いような気がして。さらに、テーマが〝子供〟っていうところでこのアルバムにも繋がるし。
――そこで、〝レテ〟(古代ギリシャ語で忘却の意味。神話に登場する、死の世界に流れる川の名前でもあり、転生する際にこの水を飲んで前世の記憶を失くすと言われる)を引いてくるのが髙城くんらしいですね。
髙城 レテの川ってまさに(Part.1で話した)生きてる世界と死んでる世界の間に流れてるボーダー、境界線ですけど、そこで前世の記憶を忘れないまま遊んでるイメージ。だから、「忘却(レテ)の水は飲まない」っていう。
――『Obscure Ride』の時に言っていたのは、髙城くんにとって生まれたての子供っていうのは、生と死の境界にいるような存在なのだと。生命力が漲っているけど、何処か死の世界の記憶も宿している。
髙城 そうですね。(Part.1、2の)繰り返しになりますけど、(『Obscure Ride』をつくっている時は)病気になって死に向かってく母親と一緒にいて、生と死の間(あわい)にいる状態みたいなものを見てたわけです。そして、その後に子供が生まれくると、奇妙なことに0歳から1歳くらいの時期もまるで間(あわい)にいるような感じがして。あの時期の子供って、宙を見るというか、視点が合ってないでしょう。それで、「ちゃんと見えてるのかな?」と不安になって覗き込むと、不思議な色をしてる。青みがかったガラス玉みたいな。そこに自分が写っていて、「死にそうになってる時の母親の目と同じだ」と、ハッとしたんです。それが強烈に印象に残ってたし、表現者として何が書きたいか? ということになると、どうしてもそのことにフォーカスが合ってしまうんですね。
――「信じるかい?/何にでもなれるのさ/どこへでもいける/境界線に遊ぶ子どものように/美しく不敵に/get back」というサビは、聞き手に訴えかけているとも取れる、このアルバムでは珍しく、強い言葉ですね。
髙城 この歌詞を書いてる時は「(『POLY LIFE MULTI SOUL』の)ソリューション的な役割の曲をつくらなきゃ。だから、強い言葉を入れよう!」と思ったんですけど、そうしたら、あらぴーからタイトル曲が上がってきたんで、「あっ、大丈夫っぽいな。でも、書いちゃったしなぁ」って(笑)。結局、エンディング前の盛り上がりみたいな感じでアルバムの流れにはまったから良かったんですけど。
荒内 (「レテの子」と「Poly Life Multi Soul」は)同じ日にデモが上がったんだよね。
――ちなみに、(Part.1で)アルバムの制作において、まずは荒内くんが新たな方向性を示し、その上で髙城くんも「リズムやコードによって選ばされる言葉が変わってくる」。そして、「「言葉を選ばされてる」ような感覚からふと出てきたのが〝川〟っていうワードで」と言っていましたが、改めて〝川〟の象徴性について考えるところを聞かせて下さい。
髙城 最初は無意識で選んだ言葉のひとつとして〝川〟があったんですけど、(次の楽曲)「Waters」なんかにはっきりと表れてると思うのは、源流の方は自然の中を流れていて、それが下流に行くとギラギラとした都市の中を流れていて。でも、それは同じ川であるわけで……。あるいは、身近なところで言うと目黒川みたいな川が昔からそこに流れていて、恐らく未来のアジアン・フューチャリズム的な世界でも流れていて……と考えると凄くSF的だなと思ったりとか。
――レテの川は生と死のボーダーだという話がありましたが、そこでも川が自然と都市を、過去と未来を繋いでいる。
髙城 そういうふうに、もともとは無意識で選んだものでも、書けば書くほどイメージが浮かんできましたね。例えば、芸事をやってる人間を河原者って呼ぶじゃないですか。やっぱり、境界にはそういうアウトサイダーが集まるっていうか、運命的なものを感じたりして。「自分たちも、現代の河原者と言えるんじゃないか」みたいな。
■10. Waters 【Composed by 荒内佑 Lyrics by 髙城晶平 Melody composed by 髙城晶平 / 荒内佑】
――そして、今も話に出た「Waters」ですが、これもまた何と形容すればいいのか分からないタイプの曲です。トラップを取り入れたビートダウン・ハウスというのか。
荒内 ビートダウン・ハウスは好きですね。ただ、この曲の場合は3拍子にすることで、さっきも言ったような捻りを加えていて。なおかつ、「魚の骨 鳥の羽根」を引っくり返した構造になってる。あっちは4拍子ベースのクロスリズムで3拍子に展開するわけですけど、こっちは3拍子ベースで次第に4拍子に展開する。それと共に、「魚の骨 鳥の羽根」の野生的なイメージをこっちでは都市的なイメージに反転させてるっていうか。
テクニカルなところでいうと、打ち込みでデモをつくって、髙城くんに歌詞を書いてもらおうとしたんですけど、凄く日本語を乗せづらそうで。
髙城 最初、英語で書いてたもんね。でも、それだと普通というか、よくあるような感じに収まっちゃうから「やっぱり、日本語で書かせてくれ」と言って書き直した。
荒内 そのおかげで、こういうトラックにちゃんと歌詞が聞き取れる日本語の歌が乗ってるっていう、前例がないものになったんじゃないかと思います。それと、今回、ヴォーカル録りの時に気を付けたのは、ニュアンスを消すこと。しゃくったり、フェイクを入れたりっていう表現は抑えて、言わばシンセ的に歌ってもらって。
――『Obscure Ride』の時はR&Bの影響を直接的に受けている時期だったので、フェイクを多用していたように思うんですが。
荒内 それを今回は減らした。結果、トラックと調和して、いなたさがなくなったんじゃないかなと。それは、こういう3拍子のビートダウン・ハウスみたいなものにどうやって日本語をのせるかと考えた時に、ゲットしたやり方のひとつですね。
――タイトルからして「Waters」ですが、歌詞も「同じ場所にいながら 異層に生きるものたち」というリフレインとか、クライマックスに向かっていよいよアルバムのテーマが前景化する感じがありますね。
荒内 そうですね。髙城くんは意識してないだろうけど、チャイナ・ミエヴィルの『都市と都市』っていう小説の世界観にも似ていて。ふたつの都市が同じ場所に、モザイク状に存在していて、片方の都市の住人はもう片方の都市の住人を見てはいけない決まりがある、まさに「同じ場所にいながら 異層に生きるものたち」を描いたSFなんですけど。
髙城 ちなみに、「Waters」っていうタイトルはあらぴーが付けたんですけど、この曲とか、「魚の骨 鳥の羽根」「Buzzle Bee Ride」とか、あらぴーがつくった曲は、もともと、〝Modern Steps〟〝Modern Steps2〟〝Modern Steps7〟みたいに一連の作品として仮タイトルがついてたんですよ。それでレコーディングの終盤になって、改めてひとつひとつタイトルを考えていったっていう。
荒内 「Waters」はぎりぎりまで「Modern Steps」が本タイトルでいいんじゃないかっていう話をしてたんですよね。ただ、それだと如何にもリズムに凝ってるってことを強調してるみたいというか、音楽にフォーカスが合い過ぎるのが嫌で。やっぱり、言葉からも世界観をイメージして欲しい、そうでないとceroでやる意味がないと思って、凄く悩んで「Waters」とつけました。
――〝Modern Steps〟は、結局、イントロのタイトルになったわけですけど、もともとは(Part.1のリードにあるように)現在の編成が始まった16年のツアーのタイトルですよね。そこには、どんなイメージが込められていたのでしょうか?
髙城 ツアーの時は、単純に11月から始まるスケジュールだったので(武満徹の)「November Steps」を引用したんですよね。そこに、新しいコンボ、新しいceroを披露するっていうニュアンスを重ねた。新曲もその新しいコンボのためにつくったから、便宜上、〝Modern Stepsシリーズ〟と呼んでた感じですね。
荒内 「バンド名(cero=Contemporary Exotica Rock Orchestra)に入ってる〝コンテンポラリー(現代)〟ではなくて、どうして〝モダン(近代)〟なんだろう」ってことは自分でも考えてたんですけど、今回のアルバムでやったような〝リズムに凝る〟ってこと自体が、実はひと昔前の取り組みなんだと思い至ったんです。今はもうちょっとセンス良く、さらっと気付かれないようにやるのが主流なのに、このアルバムのやり方は派手でしょう。ただ、だからこそ希少価値があるというか、面白いんじゃないかと。
髙城 それと、「Waters」に関して思うのは、今回のアルバムはアフロ・ビートを取り入れたことが指摘されがちだけど、ハウスからも影響を受けるところが大きかったのかなって。
荒内 確かにリスナーとしてはハウスを聴くことが多くて。だからと言って、ceroでそのままハウスを取り入れると、いわゆる4つ打ちロック的なものになってしまう。そうならないために、アフロ・ビートだったりジャズだったりを経由してるんですけど、感触としてはハウシーな楽曲が多いと思うんですよね。(最後の曲)「Poly Life Multi Soul」の後半で4つ打ちが入ってくる、そこを目指して、アルバムを通してリズム面でかなり色々なアプローチをしたというか。
――歌詞にも〝ダンス〟や〝フロア〟〝パーティ〟と言ったワードが頻出しますよね。
荒内 ハウスのパーティって、例え真面目に聴いてなくても、それをとやかくいうひとはいないじゃないですか。ロックフェスなんかで同じことをやると「あいつなんだ」みたいな感じになる。ハウスのパーティの方が社会的にも音楽的にも成熟されてるなと思うんですよ。 でも、岡山の<YEBISU YA PRO>でceroとユアソン(YOUR SONG IS GOOD)のライヴがあった時(2017年7月8日)、アフターパーティでジュン(サイトウ "JxJx" ジュン)さんと川辺(ヒロシ)さんがDJをやっていて、深夜、おれも踊ってたんですけど、ある時、ふと足を止めて、「自分は一体何をしたいんだろう?」って。
髙城&橋本 (笑)。
荒内 いや、ちょうどこのアルバムの制作中だったんで、「ハウスってこんなに踊れる曲が多いのに、自分がつくってるのはどうしてあんなに変な曲ばかりなんだろう」と考えてしまったのね。で、思ったのは、「それでも、やっぱり踊らせたいんだ。ただ、ハウス・ミュージックっていうものはこんなに成熟してるわけだから、自分がそれと同じようなものをつくってもしょうがない。むしろ、それを1回壊して、再構築するようなものがつくれたら理想なんだろうな」と。
――YOUR SONG IS GOODもエキゾを経由し、ハウス・ミュージックに影響を受けて音楽性を発展させたバンドですけど、ceroとはアウトプットがまた違うところが面白いですよね。
荒内 そうですよね。おれは、ジュンさんと視点は違えど、同じものを見てる感覚はありますけどね。
――「Waters」はアルバムのトレーラーにも使われ、リード・シングルとして12インチ・ヴァイナルでもリリースされました。オープニングで、MVにもなった「魚の骨 鳥の羽根」や、ラストの「Poly Life Multi Soul」と同様、アルバムを象徴する曲と言っていいですよね。
髙城 そうだし、「レテの子」とか「Poly Life Multi Soul」がソリューションだとしたら、問いかけの曲ですよね。だから、アルバムの中でひとが最初に耳にするのはこれがいいんじゃないかと思ってトレーラーに使ったんです。
(つづく)