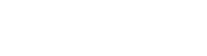
■01. Modern Steps 【Composed by 荒内佑】
――まずはイントロダクションですが、制作の順番としては終盤に取り組んだ楽曲ですよね。
髙城 いちばん最後に出来ましたね。いつも、大体、そうなんです。1曲目は最後の方に出来ることが多い。
――前作『Obscure Ride』のイントロ「C.E.R.O」はディアンジェロ「Playa Playa」を下敷きにしたジャムっぽいトラックで、アルバムがゆっくりと幕を開ける感じでしたが、今回もそういうイメージですか?
荒内 今回のイントロは逆に全部決まってるっていうか、1音、1音、デモ通りにやってもらってる、アルバムでは唯一の例外で、なおかつ、演奏はいちばん難しい。曲調がリラックスしてるから、難しくは聴こえないと思うんですけど。かなりリズムで遊んでいて、アルバムの導入にこういう曲を配置したらコンセプトが分かりやすいかなと考えてつくりました。あと、(Part.1で話した)「かわわかれわだれ」っていう作中で繰り返されるフレーズもここで初登場させてる。
――演奏は荒内くんがキーボードと打ち込みで、橋本くんがギター、髙城くん、小田朋美さん、古川麦くんがヴォーカルで参加しています。橋本くんは、荒内くんから演奏で求められることは難しかったですか?
橋本 うーん、そうですね。この曲に限らず、いきなりは弾けないですからね。最近の曲は。(2016年夏にデモが出来た)「魚の骨 鳥の羽根」もようやく弾き方が分かってきた感じで。
荒内 でも、アルバムをつくってる途中で鍵盤の比重が重くなりそうだったから、ギター主体で進めたいなと思ったんですよ。なので、この曲もそういうつくりになってる。
髙城 言ってたよね、「急にギター・ブームがきた」って。
荒内 ミーハーな話ですけど、フランク・オーシャンの「ムーン・リバー」みたいなギターっていいなと思って。最近のエッジな音楽って、ああいう朴訥としたポロン、ポロン、みたいな演奏が少ないじゃないですか。それでいて、あの曲のギターには新しい質感があったから。あと、はしもっちゃんを改めてギタリストとして使うのは面白いなと。
――以前も、橋本くんはギタリスト然としたギタリストではないという話になりました。
髙城 はしもっちゃんって言わばシンセ的なギタリストで、これまで、ceroにはあらぴーとはしもっちゃんっていう、シンセ的役割を担うプレイヤーが2人いたわけだけど、そこに小田ちゃんが入ったことで、はしもっちゃんの立ち位置が変わっていったところはあるんじゃないかな。
橋本 「Modern Steps」に関しては、リズムは難しいんですけど、弾き方とかコードとか、自分がもともと好きなジャズの素朴な面もあって、その両面性が好きですね。
荒内 自分としては、実はこれがいちばん今っぽいというか、(ブラジルの)ミナス新世代みたいな、難しいことやってるんだけど難しく聞こえない感じをやりたかったんですね。
――『POLY LIFE MULTI SOUL』の、cero、光永渉、厚海義朗、古川麦、小田朋美、角銅真実という編成に関して言うと、最早、お馴染みという印象がありますけど、本格的なレコーディングは今回が初めてですよね。それも、ライヴを積み重ねてきたからこそスムーズに行ったという感じでしょうか。
髙城 それにしても、2016年の秋から始まって、2017年を通してこんなメンバーでライヴと曲づくりが出来たわけだから、凄く贅沢だったなと思いますね。アレンジにしても皆がかなりの割合を考えてくれたし。だから、今回のアルバムはこれまででいちばん、良い意味で外部の力に頼ったというか、頼れたものになりました。
――アレンジを固めて行く際、プレイヤーのアイディアをどんどん取り入れていったと。
髙城 そうですね。設計図としてのデモはあるけど。
荒内 デモを聞かせる時は、おれがつくったのはエンジンと車輪くらいで、「こういうリズムと和声環境がありますよ、この中で好きに演奏して下さい」っていうプレゼンのつもりなんです。だから、スキーで言うなら「A地点からB地点に行くまでに、この旗とこの旗をタッチして下さい」ってルールを設定して、「途中のルートは各自にお任せします」みたいな感じなんですね。具体的には「○拍目のここにアクセント入れてください、音は任せます」みたいな。その演奏はいつも違っていいし、あるいは同じでもいいし。いわゆるジャム・セッションとは違うけど、メンバーには凄く頼ってますよね。そもそも、アテガキっていうか、この8人で演奏することを想定してつくってるので。
■02. 魚の骨 鳥の羽根 【Composed by 荒内佑 Lyrics by 髙城晶平 Melody composed by 髙城晶平 / 荒内佑】
――そして、先程(Part.1で)も色々と話しました、実質的なオープニングとなる「魚の骨 鳥の羽根」。
荒内 この曲に限らず、おれのデモを髙城くんに渡す時点ではコーラスとフックと目立つメロディはつくって、いわゆるヒラウタは空けてあるんです。ヒップホップで言うところの「フックはプロデューサーが書くけど、ヴァースはラッパーにお願いします」とか、ジャズで言うところの「テーマはつくるけど、ソロはお願いします」みたいなやり方でポップ・ソングをつくれば面白いかなと思って。
髙城 「魚の骨 鳥の羽根」は、まず骨組みを完成させようということで、ceroの3人とみっちゃん、義朗とで何回かスタジオに入って。初日、皆がセッションを始めた時に、僕は歌詞を書かないことにはそこに参加出来ないから、スタジオの隅で一気に書いた。ただ、その時点の仮歌を聞き返すと、曲の構造というか、ルールみたいなものを理解してないなって感じで。それがライヴで歌い続けてる内に、さっきアラピーが言ったA地点、B地点が見えてきて、譜割が固まったんです。
――歌詞は冒頭からアルバムのキーワードとなる〝水〟という単語が出てきますが、不穏な感じというか、体内で何かが蠢いて徐々に変態していく様子を描いているような。
髙城 〝二重化〟してるっていうかね。まず、ポリリズムとかクロスリズムみたいなところに特徴のある曲なんだっていうことは分かったから、そこを言語化しようと思ってこういう歌詞になっていったんです。あと、あらぴーから数少ないオーダーとして、「『トゥルー・ロマンス』みたいな感じがいい」という意見があって。
――『トゥルー・ロマンス』(脚本:クエンティン・タランティーノ、監督:トニー・スコット、93年)ですか。名作ですけど、このアルバムのイメージとは違うので意外です。
髙城 「異常なラヴ・ストーリーがいい」と言ってましたかね。「あと、狂ったキス・シーンを入れて欲しい」って。で、「キスかぁ、カタカナはちょっと……〝口づけ〟でもいい?」みたいな(笑)。
荒内 『トゥルーロマンス』の女の子はコール・ガールだったのが恋愛で頭がおかしくなって、最終的には銃を乱射するじゃないですか。それが「変態していく」というイメージに重なると思ったんです。
あと、デモをつくってる時に考えてたのは、音楽性と文学性を混同することが面白いんじゃないかと。この曲は4拍子と3拍子のポリリズムになってるんですけど、仮に4拍子の方に人間性を割り振って、3拍子のほうに野生、獣を振り振って。それが同時進行しつつ、最後の方で獣が勝るっていう。そういうコンセプトをあらかじめ作曲の仕組みの中に入れておいて。
――面白いですね。髙城くんは「リズムやコードによって選ばされる言葉が変わってくる」と言っていましたが、その逆と言うか、言葉が音楽を規定するという。
荒内 ある意味でマジック・リアリズム的というか、現代の科学と錬金術がごっちゃになってるような。
――荒内くんが(Part.1で)言っていた、初期のライヴでは、踊るには複雑な曲だと思われていたけれど、録音作品としてはそう思われないようにしたというのは、具体的にどんな風にアレンジを変えたのでしょうか?
荒内 例えば、最後の方で3拍子が勝つところで、4拍子のリズムを強めに残すっていう。タンバリンをずっと4で打ったりとか、小田ちゃんにはリズムが変わってもキーボードをそのまま弾いてもらうとか。ただ、それをあまりやり過ぎても図式的になっちゃうので、バランスが難しいんですけど。
――それにしても……失礼ですけど、これがceroかと思うほど演奏に聞き応えがあります。
荒内 この曲はほぼ一発録りなんですよ。
――今回、特に厚海くんのベースが変わったような。
髙城 「魚の骨 鳥の羽根」は義朗が3拍子の獣部分を担当してる。
橋本 うん、ハマってる。
髙城 獣役、適役だよね(笑)。
荒内 この曲は、セッションでつくりあげていったから作曲はそんなにしてないとも言えるんだけど、ベースだけはかっちり書いてあって。さらに、義朗と相談しながらどんどん研ぎすましていきましたね。もっと格好良く、もっとシンプルにって。ベースは頑張りました。
■03. ベッテン・フォールズ 【Composed by 髙城晶平 Lyrics by 髙城晶平】
―――ここからは2曲続けて髙城くんの曲。「魚の骨 鳥の羽根」のアフロ・ビートからがらっとリズムが変わります。
髙城 「ベッテンフォールズ」は、自分なりにこのアルバムについて考える中で、ジェフ・パーカーの新作(『The New Breed』)が出たこともあって、シカゴ音響派……アイソトープ217とかを聴き直したりしていて。
――最近のジャズの文脈で再評価されていますよね。
髙城 そうそう。改めて聴き直すとまた違った文脈に感じられるし、結構、今っぽいし。ジャズやR&Bを下敷きにするだけでなく、ここからもアルバムの〝リズム〟ってテーマに接続出来そうだなと考えて、「ベッテン・フォールズ」を書き始めたんです。
――実際に出来上がった曲からシカゴ音響派はイメージしなかったですけど。
髙城 リズムはロッキンですよね。ズッタンズッタンズッタンズッタンみたいな。当初のアイディア……僕がつくったデモではドラムはブラシの音で、ダッダッダッダッみたいな軽い音だったんです。みっちゃんにも参考にザ・シー・アンド・ケイクを聴かせたりして。そこからアレンジを練って行く中でもうちょっとパワフルになった。これまでceroではやっていない感じだし、始まった瞬間、ちょっとびっくりさせられないかなということも考えましたね。そういう意味でも、自分にとってはトライアルな曲。
荒内 それで、フックになるとリズムがたおやかになる。滝の曲だから、どばーっと落ちて行くようなパートと、どぶんと水の中に潜るようなパートをつくって、その流れに身を任せられる感じにしようと。
――この曲では、岩見継吾さんがコントラバスを弾いています。
髙城 岩見さんにお願いしようということはレコーディングのギリギリになって決めたことなんですけど、オブスキュアな感じの曲にしたかったので、ロックっぽいドラムに対してコントラバスだと絶妙なバランスになるんじゃないかと。実際、凄く良かったですね。
――この不思議なタイトルは?
髙城 これは、パラレル・ワールドっぽさを出そうと架空の滝の名前を考えて、〝ベッテン(別天)〟という地名を思いついて。何処かにありそうだけど調べたらなかったんで、こりゃいいなと。
■04. 薄闇の花 【Composed by 髙城晶平 Lyrics by 髙城晶平】
――「薄闇の花」は「ベッテン・フォールズ」とBPMがほとんど同じですが、一転、ジャジーで、ムードもしっとりとしていますね。
髙城 「ベッテン・フォールズ」がトライアルだったのに対して、「薄闇の花」は自分が以前から得意としてる感じの曲で、単純に踊らせることを考えてつくりました。ただ、サビの男女混成の掛け合いは今の編成ならではですよね。こういうことが出来るのは嬉しい。
――サビは「このテンポ このテンポで(踊ろよ さあ 踊ろよ さあ)」という歌詞ですが、今回のアルバムでは〝踊る〟という言葉だったりイメージも頻繁に登場します。
髙城 そうですね。ただ、ダンスと言っても幅広いものなので、曲によってイメージは違いますね。「薄闇の花」に関しては、やっぱり、男女で踊ってるイメージなんですけど、フロアにぎっちりひとがいる中でくんずほぐれつというよりは、自宅で、ふたりっきりでレコードをかけて踊ってるような感じ。松岡正剛さんの『フラジャイル』という本に薄明かりの文化とか、黄昏時、トワイライト・シーンみたいなことが書かれてて、そういう考え方にあてられてつくった曲でもあります。
――洒落た曲ですよね。
荒内 「スティングっぽい」って皆に言われてたよね。ブリティッシュな感じ。
髙城 UK・レゲエっぽいっていうか、ちょっと裏打ちが入ってるからね。アレンジは、全然、レゲエではないんだけど。
――前半にこの「薄闇の花」や次の「遡行」のような洒落た曲が置かれていることが、アルバムを聴きやすくしているなと。
髙城 あらぴーの曲はハイパーっていうか、大きい世界を描いてるので、だからこそ、アルバムを通して聴くと「薄闇」とか「溯行」みたいな楽曲が効いてくるなと思って並べて行きました。
■05. 溯行 【Composed by 橋本翼 Lyrics by 髙城晶平】
――コーラスに続いて始まるサンバっぽいギターは麦くんですかね。彼のソロ・アルバムの世界観にも通じるような。
橋本 そうです。こういうギターが上手いと知ってるから、弾いてもらって。
髙城 この曲は最初のデモの段階からかなり変わったよね。
橋本 髙城くんがデモを聴いて、そこに入ってたガット・ギターを軸にしたらいいんじゃないかと言ってくれたんですよね。
髙城 その後、スタジオに入ったんだけど、小田ちゃんとかみっちゃんも色々とアイディアを出してくれたり、この曲がいちばん皆でつくった感じがある。
橋本 そういう作業の進め方も含め、結果として今のceroっぽい曲になりましたね。
髙城 「おっ、はしもっちゃん来たな!」と思ったのは、ある時、冒頭のコーラスを考えてきたんだよね。
橋本 あの「ラーラーラーラーラーララー」みたいなやつ、最初はなかったんですよ。
髙城 それと、後の方に出てくる、3拍子で歌ってるリズムと後ろの演奏がどんどんずれていくっていう構造をはしもっちゃんが提案した時もあがったよね。あらぴーも「いいのつくってきたなぁ」と言ってた。
荒内 そうそう。時間がかかったけど、「これで出来た!」って。
――ceroって、これまでは各々がDTMでデモをつくり込んで行く感じだったと思うんですけど、今回はやっぱりセッションをして、アイディアを出し合って、というつくり方なんですね。
橋本 (Part.1で話したように)リズムについて考えてた時はパソコンに向き合う時間が長かったんですけど、その後、スタジオに入ってバランスが取れた感じがありましたね。
――歌詞はどうでしょう。
髙城 はしもっちゃんの最初のデモはもうちょっとわいわいしてる感じで、それで何となく〝ジュブナイル〟(〝少年期〟、及び〝少年少女向けの作品〟の意)っていう言葉をイメージして。ちょうど、『ストレンジャー・シングス』を観てたからなんですけど、ああいうものを書きたいなと。ただ、アッパーな曲の上でジュブナイルについて歌っても文字通り子供っぽいなと思って、演奏をぐっと落ち着かせた上で、もうちょっと、誰しもが持ってる好奇心みたいな感じにテーマを広げたんです。
――「あれは夢だった 幻だった 妄想だった/はずだったのに なぜ 今 ここにいるのか」とか、「この前までリアリティがあったはずだった/この世界 なぜかすっかり 脆くみえる」とか、髙城くんの歌詞においてはお馴染みの世界観ですよね。現実が揺らいで見えるという。
髙城 そうですね。それと、この曲の前に「Afro Atom」っていう仮タイトル……最終的に(9曲目の)「レテの子」になった曲の歌詞を書いてたこともあって、そこに〝子供〟の視点を掛け合わせたい、みたいな気持ちもあったのかな。
―――そこで〝子供〟に象徴させたものは何なのでしょう。
髙城 うーん……さっき(Part.1で)もちらっと言いましたけど、前作の『Obscure Ride』はうちの母親が死んだすぐあとにつくったんで、自分としても死んでくような気持ちだったし、生きてる世界から死んでる世界にいくイメージで最後の「FALLIN’」を書いて。でも、今回はその後の3年間、逆に子供が育ってく過程を共にしながらつくった。子供のエネルギーって凄いんで、いっときは自分のエネルギーを奪われて、ちょっと鬱っぽくなったりとかしつつ。(EP『街の報せ』収録曲)「ロープウェー」にはそれが表われていたりするんですけど。でも、やっぱり、子供からは与えられるものがとにかく大きいし、思いもよらなかったような光景をすごい見るし、その影響で今回は死んでる世界から生きてる世界に流入してく、強い矢印みたいなものが表れてるなって。このアルバム自体、エネルギーがあるから。曲もエネルギーに満ちてるし、男女が声を合わせて歌ってるし、ライヴでやっててもすげぇ「生きてるなぁ」って感じがするっていうか、ビートの中で生を感じるんですよね。それで、歌詞を書く上でも〝子供〟っていう言葉に行き当たったのかな。
――子供を通してパラレル・ワールドが垣間見える感じはありますよね。
髙城 例えば、子供が街中でしゃがみこんじゃって、早く行こうよって言っても動かなくて、一緒に30分しゃがみ込みながら街を眺める経験とか、普通、大人になったらないじゃん。
――(8曲目の)「Double Exposure」の「子どもの背丈で/街を眺める午前五時/全てが違って見える気がした/一日中」という歌詞はそういうことなんだ。
髙城 そうそう。比喩じゃなく、マジで違って見えるじゃないですか。大人は公園に座り込んで、砂をこんなふうに(手をすり合わせる)はやりたくない。手が汚れるって分かってるから。でも、子供はやる。で、自分も子供の頃はやってたっていう。だから、それに付き合ってたら自分の子供の頃がぱっとフラッシュバックするみたいな。
――蟻とか久し振りに見たな、そういえば、足元にはこんな別の世界があったんだよな、みたいな。
髙城 そうそうそう。『POLY LIFE MULTI SOUL』っていうタイトルにも関わってくる話だけど、自分の子供の視点に立つだけでこんなに違うんだから、僕と他のひととでは、全然、別のものが見えてるわけで。単純にそういうことが面白いなって思ったりしてましたね。
■06. 夜になると鮭は 【Composed by 橋本 翼 Lyrics by Raymond Carver / 村上春樹】
――これは、橋本くんがリズムに関して試行錯誤していた頃のトラックだと(Part.1で)言っていましたね。
橋本 以前から個人的に、ジャズの演奏をサンプリングしてビートに乗せる、みたいなことをやってたんですね。これは、そこから一歩先へ行けないかなと思っていろいろと試していく中で出来たものですね。リズムで引っ張るというよりフレーズで展開させるというか、ビートはあるけどそれで身体を動かすのではなく……。
髙城 もっとアンビエント的なものというか。
橋本 ドラムのリズムとピアノのリズムがどんどんズレていくんだけど、何処かで合ってるみたいな感じが面白いかなって。
――そのトラックの上で髙城くんがポエトリー・リーディングをしています。テキストはレイモンド・カーヴァーの詩を村上春樹が訳した「夜になると鮭は」。これまでもceroは様々なフレーズを引用してきましたけど、他人の詩をそのまま使うということは、カヴァー以外では初めてですよね。
髙城 単純に好きな詩を読んだということなんですけどね。
――(EP『街の報せ』収録曲)「よきせぬ」の歌詞について、「ずっとカーヴァー的なものをやりたいと思ってたんですけど、今回、そういうものがちゃんと出来たなって自負してます」と言っていたように以前から好きな作家ですよね。
髙城 そうでなんです。まず、はしもっちゃんが出してきたトラックに詩を乗せようと思ったきっかけが、この間、サニーデイ・サービスのアルバムで朗読をしたんです。
――3月に発表された『the CITY』収録曲「ザッピング」。
髙城 「ザッピング」は、曽我部(恵一)さんから「歌でもいいしラップでもいいし朗読でもいいし、何でもいいから声を乗せて下さい。iPhoneの録音で構わないんで」とオファーされて。その時、「詩の朗読っていいな」と思ったんです。
で、あれは自分で書いた詩なんですけど、映画を観てると主題にまつわるテキストみたいなものが、観客に向けて提示されることがあって。例えば、去年の『ブレードランナー2049』だったら、(ウラジーミル・)ナボコフの『青白い炎』が象徴的に使われてて、「恐ろしく鮮明に高く白く戯れる噴水」って引用が何回も繰り返されたり。それは、その作品がある種の裏テーマになってて、内容を知ってたらより読みを深められるっていう。そういうコンテキストのヒントみたいなものをアルバムに入れ込む、映画的な……音楽ではあまりないつくり方を試してみたいなと考えたんですね。「夜になると鮭は」を使うことで、前の曲が「溯行」なんで鮭の遡上にもかけられますし、アルバムに通底して流れる〝川〟の意味を深めたいなと。
(つづく)